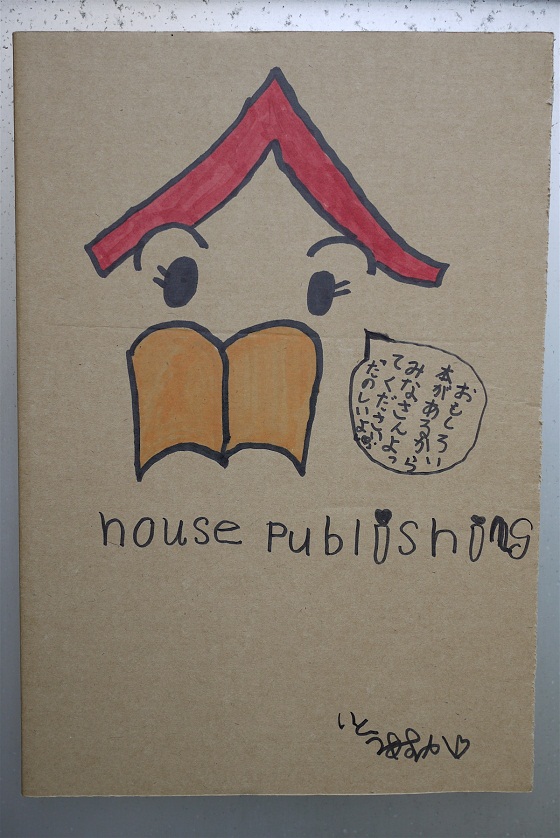
2011年7月8日、ダンボールで家具を製作し、避難所や幼稚園・託児所を支援する活動をしている藤村和成さんに会いに、気仙沼へと車をとばした。

気仙沼出身の藤村さんは、東北大学大学院建築学科在籍で、現在2年目の休学中。
昨年度は、語学留学で上海に一年間滞在した。その頃からぼんやりと、自作の家具と古本を一緒に販売出来たらというアイデアがあった。
残りの休学期間をイスラエルでのボランティア活動にあてようと、準備のための健康診断を終えたその日、自宅で被災した。
高台にある自宅は、幸い瓦が落下した程度で建物自体の被害は少なく、家族も皆無事だったが、電気もガスも不通のまま、津波で街がどのようなことになっているのか知るすべもなく、一夜を過ごした。
「何もすることがなくて、なぜか上ばかり見てしまう。そしたら、真っ暗な空にすごい数の星が見えた。一生忘れないと思う。」

実家近くの空いていた工場を工房とし、すぐに避難所やボランティアセンターに足を運び、情報を収集し始めた。見えて来た問題は、すぐにでも必要であろうと思った避難所の間仕切りが断られるという事実だった。
「震災直後の避難所の方々は、泣いているような怒っているようなよくわからない表情だった。
真っ赤に血走った目をしている人もいて、余計な刺激は一切いらない、という雰囲気があった。」と藤村さんは話してくれた。
避難所内での間仕切りは、その導入のタイミングがとても難しいのだそうだ。
「ここは仲良くやっているから、そんなのいらないよ」 と断られることが多かったと言う。
また、皆の手前、仕切りが欲しくてもなかなか言えないというケースもある。
それぞれのスペースの確保、境界線争いなどの問題があり、管理側も当初は極力トラブルを避ける傾向にあったようだ。

「間仕切りが、家族のような雰囲気を阻む”壁”になってはいけない。
何ヶ月にも渡る避難所生活で、プライバシーを守る間仕切りが必要でない避難者など1人もいない。house publishing がすべきことは、間仕切り設置によってみんなが家族のような雰囲気になれるような仕組みを考えること。」 と藤村さんは話す。
「ダンボール」という言葉のイメージが誤解を招き、「犬小屋に住まわせる気か。そんなもの自分たちで作れる。」といった調子で断られたこともあったが、何回か通って、間仕切りの実物を持って行って見せると、「いいね!」とその場で注文がもらえたという。
気をつけていることは「相手の話を聞くこと」「営業行為ではないので押しつけはしない」「被災者感情を逆なでするようなことはしない」という点。
全て先輩や経験者の方から学んだことだ。

藤村さんの作品は、地域の人とのコミュニケーション無しでは成立しない。
設置場所である現地に何度も足を運び、入念に相手の要望を聞き、デザインを考え、幾度も作り直し、完成したものを自ら届けに行き、そこでまた次に必要なものがはないかと耳を傾ける。その過程ひとつひとつを藤村さんはとても大切にしている。

午後、実際に作業を手伝わせてもらい、しばしダンボール相手に汗を流していると、工房にひとりの男の子が遊びに来た。
最近では、預かり物の絵本やおもちゃなどを置くフリースペースが出来て、近所の小学生が自由に工作をしに来たり、ちょっと寄り道がてらおしゃべりをしに来る場所になっている。
工房に入るなり、「今日はあと8分しかいられないんですけど」とすぐさまダンボールを手に取るK君。七夕だから何か書いて、と藤村さんが手渡したダンボールの短冊に、
「ダンボール職人になれますように」と力強く書いたK君に皆で度肝を抜かれた。
藤村さんの一番弟子だ。

文/中村友紀 写真/松島大介

