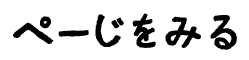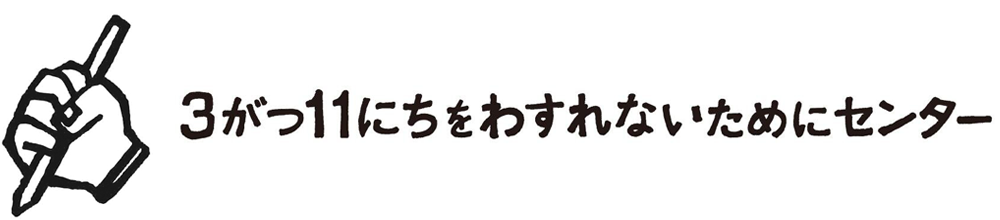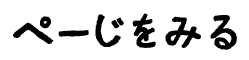

この記事は、2023年12月6日にお茶の水女子大学の授業(担当:丹羽朋子)で行った対話ワークショップの記録を、学生有志が編集しまとめたものです。
本ワークショップに参加した学生30名は、「わすれン!」に寄せられた4本の映像を視聴したのち、4グループに分かれて対話を行いました。参加者同士で映像の感想を共有し、その後「問い」について話し合いました。
このページでは、DVD『石と人』(制作:小森はるか・FIVED)を観て、「“よりどころ”とはどんなもの?」という問いをめぐり思索した対話の記録を掲載します。

*文中の話者A〜Hのアルファベットは、ワークショップを実施した際に着席していた席順を示しています。
『石と人』をめぐる対話
話者G 『石と人』の映像は2014〜2016年くらいに撮影されたとキャプションにあって、当時の被災地は全然復興とか終わってない時期で、まだ仮設住宅にも住んでるし、道路の補修も終わってない。そういう震災からの復興の最中に、そこに住んでる人たちがこんなに地元のことが好きだったんだなとか、この地元が好きだからこそ、そこに次に住む人たち、その地を受け継いでいく人たちのために神楽とか、新しい伝統を作っていったのかなと、すごく地元への愛に溢れているように思いました。
話者H 私は東京出身で、“地元愛”みたいなことについて考えたことってなくて。同じような境遇になった時に自分がどう思うかはわからないけど、ここまですごい地元のことについて考えて動いてらっしゃるのが、正直自分とはちょっと違う感覚だったなっていうか、それがすごい印象的でした。
話者F 東京のどちらですか? 地元のお祭りとかは?
話者H 世田谷。地元のお祭りはあって行った記憶もあるけど、私そんなに愛着もなくて。地元めっちゃ好きか、って言われたら、嫌いじゃないかなぐらい。
話者F わかります。私も東京出身。地方出身の方は?
話者D 私は山梨。でも、映像を見た自分の感想は地元を絡めた話ではなくて、映像の中にたびたび挟まる石のカットが印象的で。
たとえば石が映った後に、神楽を待ってるシーンがくる。ただの石の映像でも、前に映るものとのつながりによって意味が変わってくる。
あと、石は人がどうこうして作った人工物じゃなくて、自然にできてずっとその土地にあるものなので、人が持っている記憶よりも石が持ってる記憶の方が長く残るし、個人には見えていないような記憶も石が持ってるっていうふうに捉えられる。巨石は、同じ時代に生きる人たちの記憶を再生するのと、その後にその土地に住む人の記憶を残していく装置にもなっていくんじゃないかなって思いました。
話者A 私はこの映像、最初は何言ってるんだろう?っていうのが全然分からなくて。今回見た他の作品はカメラの向こうにいる、見ている私たちに話しかけたり、そもそもカメラマンさんがインタビュアーとして語り手と会話してることが多かったけど、『石と人』では撮られてる対象がカメラで撮られてるのを意識してないっていうか、ただひたすら日常を写してるなっていうのを感じて、震災の後に劇的じゃないけど、ちょっとずつお祭りだったり、今も伝統を続けてるよっていうのを語りかけたいのかなって、私は思いました。
話者B あの巨石は、最初の方に映っていた幼少期の写真、記念写真みたいに、巨石であるがゆえに街の中のシンボル的な存在として、いろんな人の記録に残り続けていく。でっかくて重い自然物であるがゆえに、町とかその他の建物とかとは違って、震災でも流されずに、震災が終わった後もその場にあり続けて、だからこそ、ただ残ったものじゃなくて、地元の方にとってより一層、結束のシンボルであったし、震災前の思い出が残っている場所でもあるのかなって思いました。だから、この石が神楽みたいに復興とかそういうものの中心地になっていったんじゃないかなって。
話者C 震災で周囲にはなんもなくなっちゃったけど、その石だけは残っているから、震災の歴史が現れるものになってるんだなって。で、その石を中心にしてお祭りやイベントが行われて、震災の記憶を残してるその石が、これからの復興のスタート地点、中心地点になっているんだな、と。
話者F 「残していく」みたいなことを強く感じさせる映像で、「悲惨な過去を映す」といったコンセプトとは違う感じがあったなって。
話者E 私は映像見る前にキャプションとか全然読んでなくて、ただボケーっと動画見てた時は、石とか全然何のことかわかんなくて、ただそこに住んでる人の日常が映し出されてるのかな、と。震災経験してない私たちはそこに住む人たちのことをあまり理解できないけど、別物とは思っちゃいけないみたいな、そういうことかなって思ったんですけど、授業で地域の人たちにとってその石の存在は、大切なよりどころであったって聞いて。そういうことって、外野の人たちにはわかんない。
お互いに話さないとわからないけど、話せるようになるには時間が必要だし、だからこそこういう記録があって、それについて話してくれる人がいて、私たちもその状況が理解できるのかなって思いました。
話者H 私は、赤ちゃんを石の上で遊ばせてたシーンが印象的でした。他の作品で映っていたのは大人とかお年寄りとか、震災の前からそこに住んでた人が中心だったんですけど、『石と人』では震災の後に生まれた子供が映像の中に取り込まれてて、それがずっと昔からある石との対比っぽいって感じました。
話者F みんなの感想を聞いて、動画の中で埋め立てられちゃうみたいな話があったと思うんですけど、それを含めてこの動画ってどういう思いで撮られたのか聞いてみたいなって思いました。どう感じました?
話者B 埋め立てられちゃうことに対する抵抗感っていうのもあると思うんですけど、やっぱり石の周りって震災から3年経った後でも草が生えっぱなしになっていたり、そんな中から自分たちで手がかりを見つけて復興しようとしていた中で、埋め立てることになってしまった。そういうことへの戸惑いとか憤りを表したり、自分たちがこういうふうに自分たちで復興しようとしていってたんだっていう記録を残すために、巨石との記録を残そうとしたのかなって想像しました。
話者F たしかに、明るい雰囲気だけど、明るいだけじゃないみたいなのはすごく感じました。埋め立てられちゃうっていうことに対する怒りかもしれないし、自分たちが復興して、これからこの土地で生きていこうっていう生命力みたいな。
——問い:“よりどころ”とはどんなもの? あなたの“よりどころ”はなんですか?
話者F 難しいな、「よりどころ」。どんなものだと思います?
この質問見て、あんまり意識したことないなと思って。
話者E 私が思いつくのは家族かな。
話者G 私は「よりどころ」って聞いて、心情面のものが最初に頭に浮かんだ。そういう意味で自分がよりどころにしてるのは、友人ですね。基本一人が好きなので一人の時間を確保したいと思いつつ、やっぱり友達といる時間も大切にしたくて。狭く深くみたいな付き合い方をしてるので、大切にしている人はごくわずかなんですけど、その人たちとは、楽しいこともつらいことも共有したくなる。そういう意味で、すごくよりどころにしてるなって感じます。
話者F たしかに。人をよりどころにしてるっていうのはありますよね。
話者B 私はよりどころって、どれだけ他のものが変わっても変わらないものじゃないかなと思って。
一人暮らしを始めてから、しんどくなるとしょっちゅう実家に帰りたいって思うんです。だからその点では、家族が私にとってのよりどころなのかな。
私の実家、引っ越したんですよ。でも帰りたいのは引っ越した先じゃなくて、引っ越す前にいた空間なんだよなって。やっぱり、人もあるけど、時とか空間とか全部合わせたものを、私はよりどころにしてたんだろうなって。
話者F ちょっとわかる気がします。自分が通ってた学校とか、昔住んでた家とか、 近くを通ると気になりはするけど、「あ、今は違う人が住んでんだろうな」って思うと何だか違う気になるし。
もう先生とかも変わっていって、自分が知らない人ばっかりになってるって考えると違う場所に思えたりするから、人も場所も含めて空間みたいなものが、よりどころになったりするのかな。
話者A 私にとってのよりどころは、精神安定剤的なものかもしれません。
私、ちょっと幼いんですけど、ブランケット症候群みたいなのを引きずってて、2歳から持ってる犬のぬいぐるみとタオルケットが大好きで、受験期とか不安な時は抱きしめたり、ぬいぐるみを肩に乗せつつ勉強してたり。それですごく精神が安定する。
親も大切なんですけど、自分の弱みを見せられない時があって。でも、物は何にも言わないし、ただひたすら私を受け入れてくれるから、そのぬいぐるみとかタオルケットを抱えて安心して、精神を安定させてたのかなって思いました。
話者F わかります。私がよりどころを挙げるとしたら、自分の部屋のクローゼットの中。
全員 (笑)
話者F 私、実家暮らしなんですけど、部屋に鍵が付いてなくて、ドアが開けっぱなしになってたりとか、人の出入りがあったりすることが多くて。ベランダともつながってるから、ベランダに行くついでに誰かが通ったりみたいなこともあって。ウォークインクローゼットにちょっと入れるスペースがあるんですけど、絶対クローゼットの中は開けられることがないから、一人きりになれる空間みたいな。きっと、私は誰かに悩みを相談したりとか頻繁にしないタイプだから、一人でいられる空間みたいなのがよりどころになるのかなって思います。
話者C 部屋の中の一部分が、みたいなの、すごくわかります。自分の部屋のベッドの上にクッション置いて、壁にもたれかかる時が一番幸せ、みたいな。
そういうのはたくさんあるけど、でも家族も思い浮かんで。家族は頼れるし安心するけど、私も全部を話すわけじゃないし、友達とかも頼れるけど、全てを明かすわけではない。でも、別に隠してることがあってもいいっていうか。全部ばらさなくても、話したいことを話せれば、それでよりどころになるのかなっていうのは思いました。
話者D 私、コミュニティに所属する意識的なものが自分の中で薄れてきてるって感じていて。というのも、自分がどのコミュニティに所属してるっていうのが一つじゃないから。
家族っていうコミュニティの一員でもあるし、大学のこの学科の一員でもあるし、サークルの一員でもあるし、いろんなコミュニティに所属してて、「自分にはこのコミュニティしかない」っていうのはないから。それぞれの所属意識によりどころがちょっとずつあるみたいな。だからこそ、「ここしかない」みたいな強い所属意識がないんじゃないかって思いました。
話者F たしかに。入ってるコミュニティごとに見られ方も違うし、自分の振る舞い方も違うし。でもそこに入ってることへの帰属意識はあるにはあって、でもその一つだけじゃないっていうのはすごくあるな。
話者H 私の友達はSNSが一番落ち着くらしくて。全然知らない人とつながって、この人たちは自分のことは何も知らないから、受け入れてくれてすごい落ち着くし、安心するみたいなことを言ってて、その時はへぇって思ったんですけど。全然知らない人に受け入れてもらうっていうのも、よりどころの一つなんじゃないかなって思いました。
話者F 確かに、Twitter(現X)とかで自分と親しい人だけでつながれるとか、近い意見を持ってる人とか、近い趣味持ってる人とかだけでつながれるみたいなのは、一つのよりどころになるような気がします。
話者B 私、さっき変わらないものがよりどころなんじゃないかって言いましたが、自分に対してネガティブなリアクションをしないって、よりどころになる上でめっちゃ大事なんじゃないかなって。
家族に全部打ち明けるわけじゃないっていう話を聞いてて、家族でも他人だし、いつだって自分のこと受け入れてくれるわけではないと思って。
話者F みんなが挙げてたものに共通してるような気がしますね。絶対ネガティブな反応をしないとか、絶対ネガティブなこと言わないとか。無意識に受け入れてもらえると思ってるものみたいな。そういうものがよりどころになるんですかね。
でも、そう考えると、自分の置かれてる場所によってよりどころって変わるんだろうな。引っ越す前の実家だったりとか、やっぱり引っ越したからこそ、実家がよりどころだなって思ったんだろうし。私は実家に住んでるから、自分の家がよりどころだなって思うけど、いざ一人暮らしをしてみたら違うだろうし、実家ごと引っ越したらっていうのもまた違うだろうし。大学卒業して、社会人になって、交友関係が変わっていったら、よりどころにしてた友達とかも変わるだろうし。よりどころって言いつつも、変わるものなんだろうな。
話者G コミュニティへの所属意識が薄れてきてるっておっしゃってたと思うんですけど、自分が年齢を重ねることで、自分の中の歴史みたいなものが積み重なって、所属している、もしくは所属していたコミュニティが蓄積されていく中で、途切れるものもあるし、複数持つことになるものもあるし。
個人的な体験ですけど、大学生になってアルバイトをまず一つ始めて。その職場は学生の子が多くて、みんなワイワイしてて仲良いし、まぁ楽しんでたと思うんですけど、たまたま別のアルバイトも始めて。そしたら今度はそっちがすごく楽しくなって、自分の中での心情と実際それに割いてる時間が二つ目のバイトの方が大きくなったんです。
一つ目のバイト先はそこに所属している自分も肯定してくれるし、楽しいし、ある程度アイデンティティを構成してくれてたところだったんですけど、すごくよりどころにしてるかって言われると、正直そうでもないっていうか。そういうのって変化していくと思うし、コミュニティへの所属意識とかも、年齢を重ねて経験値が増えるにつれて低くなっていくと、私も思います。
話者F 所属意識とかで表した時のよりどころって、さっき言ってくれた「アイデンティティ」みたいなのが近いのかな。民族的なアイデンティティとか。日本にいると「民族」とかってあまり意識しないから、「地元」とかでもいいし、どっかの集団に所属しているとかでもいいし。一つ一つへの所属意識がそんなに強くないからこそ、それぞれを統合したアイデンティティみたいなものが、みんなの中にあるのかなって。そう考えるとアイデンティティがよりどころにもなるのかな。
「こういうのを目指してるから頑張れる」とか、「こういう人たちに囲まれてるから自分もそうなりたい」と思うとか、頑張る理由みたいなものも近いのかなって思います。
話者G 物をよりどころだと思ってる人もいれば、空間的なところに意味を見出している人も、人に対して思ってる人もいる。一定の基準を定めるっていうのは難しいけど、自分に対してネガティブなアクションが起こらないとか、絶対に自分を肯定してくれるって自分自身が思えるみたいなところは、たしかにそうだなって思いました。
話者F あとは、推し活とかも近いのかなって思いました。“絶対推し”、自分のこと否定しないし、ただ癒してくれるみたいな。
話者C 私も苦しい時にライブがあるから頑張ろうって思うし、心の面ではよりどころになってるかな。
話者G 推し、誰かいます?
話者F 私は「あぁクリスマスライブ行くから頑張ろう」みたいな気持ちで。チケットが当たって、今週の土曜日ライブで。
全員 おぉー、楽しんで。
話者G たしかに推しがいるからこそできた友達とかもいる。そういうところで言うと、実際に需要と供給があって、推しの側からしたら一方通行かもしれないけど、推しているこっちからすると、自分とその他のところにもいろいろと派生していくものはあるから。
たとえば、推しから見られるかもしれないから、ライブに行くまでにこの洋服を買うためにバイトを頑張ろうとか、どんどん広がっていくところはあって。その作用もあって、推しっていう存在はよりどころの一つの要素にはなるのかな。
話者A 私もクリスマスイブにライブに行ってきます(笑)
話者E イベントとかじゃなくても、夜寝る前とかに画像とか見ると癒される。
話者G 意外とみんな、推し、いるんですね。
話者B 推しに頑張れって言われたら、別に私に言ってるわけじゃないけど、私に言ってくれているかもしれないっていうその事実だけで救われる。
全員 (笑)
話者A 歌に「大丈夫」っていう歌詞が入ってて、受験期にそこだけ聞いて「大丈夫、大丈夫」って言ってました。
話者C たしかに一方的だからこそ、こちらの自由にっていうのはありますよね。
話者E それこそ、いつ見ても変わらないっていう。
話者B 絶対ネガティブな反応はしない。
全員 たしかに、一方通行。
話者F 画面の中で変わらないところもありつつ、推しが成長してるところを見て、推しが頑張ってるから、私も頑張ろうみたいな。
話者A 全部楽しめますよね。全ての要素を楽しめる。やっぱり推しはよりどころですね。
話者E よりどころって「よる」ところだから。「よられ」どころとかだと、また違ってくるのかな。向こうからの愛情とかだとしても、来るとちょっとプレッシャーになっちゃったりするから。やっぱり物とか無機物、推しとか、絶対こっちには反応はないから、そういうものがよりどころになるのかなって思いました。
話者B さっきふと思ったのが、「よりどころ」と「依存」ってちょっと違うものかもしれないけど、全く切り離せないものではないよな、と。さっき言ったみたいに、よられるとプレッシャーを感じるし。だからこそ、コミュニティとかじゃなくて、空間、場所とか、物の方がよりどころになる人が多いのかなって思いました。
話者F たしかに、依存と何が違うかって、あんまりわかんない。よりどころがあるのはポジティブに聞こえるけど、依存してるって言われたら、なんだかちょっとネガティブな感じがするし。
話者E いい面と悪い面が見えてきちゃいますね。
話者F 「それがあるから頑張れる」とかだったらよりどころなのかもしれないけど、「それじゃなきゃダメ」「それがないと生きていけない」みたいな、自分の生活みたいなところを犠牲にしてよりどころに頼ってるみたいなのは、ネガティブに映るのかなって思いました。
話者A よりどころって複数あるんですけど、依存先って一本だから、それがなくなったらもうダメみたいな。よりどころはいっぱいあるから、一個なくなっても最悪どうにかなるみたいな感じなのかなって。
話者E よく聞くのが、依存先を増やすことが自立になるっていうこと。
最初は、よりどころってすごい大事なものだと思ったので、一つじゃなきゃいけないのかなって思ってたんですけど、今いろんな話聞いてて、別に複数でもいいのかって。
話者F むしろ複数の方がいいのかな。
話者B もし何かがなくなっちゃった時のためのストックって言うと言い方悪いけど、そういう時のためによりどころはたくさんあった方がいい。
話者A 『石と人』の中で、最初見た時は石がよりどころだったのかなって思ったけど、こうやって話す中で、石を囲ってお祭りするとか、そういう交友関係も含めて、全部がよりどころだったのかなって思いました。
話者F そんな気がします。埋め立てられちゃってバラバラになっちゃうからこそ、やってたのかなって。
でもそうなら、なんで神楽を作ったんだろう? 誰が受け継いでいくんだろう、って思ったり。「新しい伝統」って言うけど。
話者B 神楽っていう共通するものがあるっていう事実が、「あの時の神楽あったよね」って、形はないけど、人の記憶の中に残る故郷になる。
石がなくなって、共同体っていうよりどころもなくなっちゃうから、新しいよりどころとして、「もの」じゃなくて「こと」を作ったんじゃないかなって思いました。
話者F 私、映像を見た時にはなんで神楽作ったんだろう、って思ったんですけど、そう言われてみるとたしかに、新しいよりどころにするために神楽があったのかなって納得しました。
話者E 神楽をよりどころにするのもそうかもしれないし、神楽で出会った何かをよりどころにする、よりどころのきっかけを作ったみたいなのもあるかなって。
話者F たしかに。そう考えると、埋め立てられちゃうことへの怒りとかだけじゃなかったのかな。だから楽しそうに見えたのかもしれない。
でも、「よりどころってどんなもの?」って言われた時の答えを、一つにしちゃダメなのかもなって思いました。わかりやすく答えにできないのが、よりどころであるべきなのかなって。
映像に触れて、言葉を紡ぐ——「正解のなさ」と向き合った大学生の対話の記録
①今もなお住み続けるのはなぜ?——『生きられる家(1)岡田地区 吉田さん宅』をめぐる対話
②“よりどころ”とはどんなもの?——『石と人』をめぐる対話
③震災の当事者とは?——『過去を見直して、今を見つめる』をめぐる対話
④“弔う”ってどういうこと?——『参佰拾壱歩の道奥経 抄』をめぐる対話