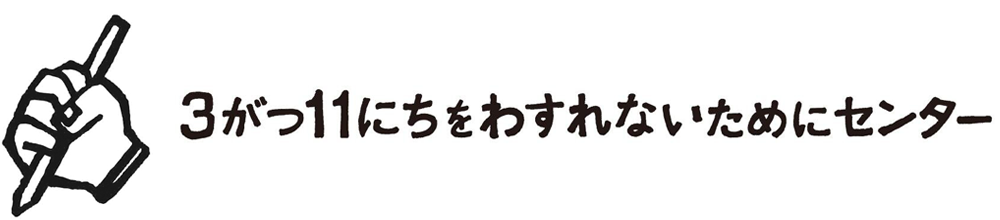![]()
2015年3月15日
2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災の津波で、石巻市立大川小学校では全校108名中、74名の児童が死亡あるいは行方不明となりました。教員も10名が亡くなっています。
108名といっても当日欠席、早退、保護者が引き取りに来た児童がおり、最終的に校庭にいた児童は70数名で、4名だけが奇跡的に助かりました。教職員も助かったのは1名だけです。学校管理下で、このような犠牲を出したのは大川小学校以外にありません。大川小より海に近い学校はもちろん、もっと海から遠い上流の学校や保育所も逃げています。
震度6という強い揺れが3分も続いた後、大津波警報が発令され、防災無線やラジオ、市の広報車がさかんに避難を呼びかけていました。その情報は、校庭にも伝わっていて、子どもたちも聞いていました。体育館裏の山はゆるやかな傾斜で、椎茸栽培の体験学習も行われていた場所です。迎えに行った保護者も「ラジオで津波が来ると言っている。あの山に逃げて」と進言しています。スクールバスも待機していました。そして「山に逃げっぺ」と訴える子どもたち。
校庭で動かずにいる間に、津波は北上川を約4km遡り、堤防を超えて大川小を飲みこみました。15時37分、地震発生から51分、警報発令からでも45分の時間がありました。子どもたちが移動を開始したのはその1分前、移動した距離は先頭の子どもで150mほどです。なぜか山ではなく、川に向かっています。ルートも狭い民家の裏を通っています。しかも、そのまま進めば行き止まりの道です。
時間も情報も手段もあったのに救えなかった、危機感を感じていながら「逃げろ」と強く言えなかったのはどうしてかを議論しなければなりません。どうして組織が機能しなかったのかです。あの日から、自分自身に言い聞かせている、重い重い言葉です。
守るべき命、しかも守ることが可能だった命を守れなかった事実から目を背けてはいけません。警報が鳴り響く寒空の下、校庭でじっと指示を待っていた子どもたちに耳を澄まし、目を凝らすのです。誰も悪意をもっていたわけではありません。でも、救えなかった、それはなぜか。先生方は、黒い波を見た瞬間「ああ、〇〇すればよかった」と後悔したはずです。その後悔を無駄にしてはいけません。
学校だけではなく、私たちの周りにある様々な概念、価値観、システムを見直すことは、東日本大震災で、現代社会が突きつけられた宿題のような気がします。その宿題は、情報や物が氾濫する一方で、多忙感、閉塞感が蔓延し、本質的な豊かさが失われつつある我が国の方向性にも影響を与えるほどの意義をもつように思います。子どもたちの命を真ん中にして、誠意をもって向き合えば、はじめはかみ合わなくても必ず道は見えてくると私は今も信じています。
大川小学校の校歌には「未来を拓く」というタイトルがつけられています。大川小は、始まりの地です。もう一度、命の大切さやよりよい学校のあり方を確かめる場所であるべきです。小さな命たちが、未来のための大切な意味を持てたとき、私たちの向かう方向で、あの子たちがニコニコ笑っている気がします。

この文章は2015年3月14日に開催された「第3回国連防災世界会議」で発表した内容です。また、2019年6月に発行した冊子「小さな命の意味を考える 第2集 宮城県石巻市立大川小学校から未来へ」にも挨拶文として掲載しています。
参考:佐藤敏郎のブログ「これまで、ここから~大川小学校のこと」
https://korekoko.blogspot.com/
写真提供:大川伝承の会(撮影日不明)