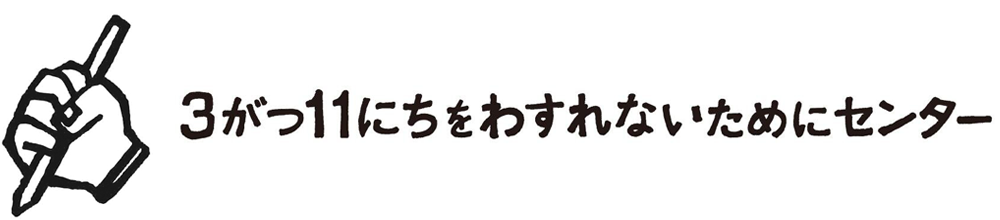福島県の阿武隈山系、浜通りの西端に位置する葛尾村は、村域の大部分が福島第一原子力発電所から20kmから30kmの圏内に入ります。それゆえ地震や津波による物理的な壊滅的被害を免れたとしても、福島第一原発事故による放射性物質が村に降下しました。放射線は肉眼では見えませんから、村内で震災による破壊の傷跡をはっきりと認められるわけではありません。しかし、村のいたるところで見かける線量計に表示される空間線量率の値からは、その場所が紛れもなく震災で被災した地域であることを突きつけられます。
私が最初に葛尾村を訪れたのは2019年の10月でした。バスに揺られ峠を越えて村に入った時、車窓に映った葛尾村の光景が忘れられません。幹線道路沿いの田んぼ一面に積み上げられた巨大なお手玉のような物体を目にしてすぐに、それが除染土の入った黒いフレコンバックだと気づきました。震災から8年が過ぎ、村民の生活空間を取り戻すために進められた除染活動の堆積が、村を横断する県道に沿って休耕田を埋め尽くしていました。農業を主産業とする村の、本来なら刈り入れ間近の稲穂が風になびいているはずの場所で、ずっしりと重い黒ビニールの袋が道路にせまり、道端の雑草だけが風に揺られていました。小学生の頃に東京で震災を経験しそれまで被災地に縁のなかった私が、人に誘われるまま葛尾村を訪れ、食堂にお昼ご飯を食べに行ったり畑仕事のお手伝いをさせてもらったりしていると、視界の端にはときどき黒袋のシルエットが映りました。東京では、節電の呼びかけも聞かなくなって久しくなっていましたが、葛尾村では、見えないはずの放射線が地元の人がトン袋と呼ぶ確かな黒山の実体として住宅や田畑や畜舎の背後にうずくまっていました。一年に数回の頻度でその後も村を訪れるようになり、村の復興が進むのを目にするようになりました。フレコンバックは村の中心部から中間貯蔵施設へ次々と運び出されていきました。そして草木の陰に残されたフレコンバックを時々見つけても最初に目にした時のような衝撃は感じなくなりました。無くなったのか気にしなくなったのか、フレコンバックが見えなくなると葛尾村は野菜の美味しい山間の普通の村でした。その頃、葛尾村出身で震災を機に村を離れつつ復興・創生インターンシップのスタッフとして村で再び働いていた松本隼也さんと出会いました。彼の実家は村の中心部から車で15分ほどの、峠を超えた先にありました。
 2021年3月16日のかげ広谷地(全村避難から10年2日)
2021年3月16日のかげ広谷地(全村避難から10年2日)
 2021年6月5日の松本家(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日の松本家(全村避難から10年2ヶ月22日)
葛尾村の北端に広谷地という行政区があり、そのさらに北端にかげ広谷地と呼ばれる小集落があります。その中の一軒の住宅に松本さんのご一家が暮らしていました。彼らがその地に移住したのは、終戦直前の1944年のことでした。疎開先を移りながら新天地を求め、かげ広谷地の山林を開墾した最初の人々のうちのひとりの女性からこの地の松本家は始まりました。炭焼き、農業、畜産と時代に合わせて生業を変化させながら、土地を拓き建物を増やし、4世代にわたって暮らしが続いてきました。数世帯だけの小さな集落ながら、確かに葛尾村の一部として生きてきた松本家の生活は、震災から3日後に断ち切られました。福島第一原子力発電所3号機が水素爆発した報を受け、3月14日に当時の葛尾村長は村を挙げて福島市へ避難することを決断しました。葛尾村のいわば末端に位置する松本家も全村避難の対象となりました。松本家の避難生活は、初めは福島市のあづま総合運動公園、次に会津坂下町の会津自然の家へと移りながら、郡山市内で借上住宅を借りるまでの約1か月間にわたって続きました。家族が去った後のかげ広谷地には家と農地が残されました。葛尾村の全村避難は2016年6月12日に帰還困難区域を除いて避難指示が解除されるまで続きました。約5年3ヶ月の年月は葛尾村の多くの人々にとって避難先で新しい生活が始まるのに十分な長さだったでしょう。松本家の家族も避難指示解除後にかげ広谷地には戻りませんでした。
松本家を訪れるまで、住まれなくなった家というのはすぐに廃墟になるものだと思っていました。人が住んでいる家と空き家の間に多くのグラデーションがあることを松本家は教えてくれました。葛尾村に来た学生たちの臨時の宿泊場所として隼也さんに連れられて松本家を初めて訪れた夜、私たちはこたつに潜り込んでテレビを見ていました。電気はちゃんとつくし、裏山の井戸水を引いてきた水道も難なく使えました。居間に飾られた旅行先のお土産や台所の食器や勉強机の筆記用具など、家中にある生活の品々が、痕跡というにはあまりにも鮮明な暮らしの後姿として残っていました。しかし住む人の息遣いだけがそこになかった。後になって、松本家の人がときおり家を訪れ畑にトラクターを入れ、家の中の換気をしていることを知りました。住まれなくなった松本家は空き家ではありませんでした。数年後のことですが、松本家を訪れた人が「テレビのセットみたい」と呟いたことがあります。物だけがきちんと生活の印を残して、松本家に震災後の時間が流れます。
 2021年6月6日の松本家の玄関(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日の松本家の玄関(全村避難から10年2ヶ月23日)
 2021年6月6日の松本家の居間(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日の松本家の居間(全村避難から10年2ヶ月23日)
 2021年6月6日の松本家のキッチン(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日の松本家のキッチン(全村避難から10年2ヶ月23日)
私たちは2021年6月の初めにまた松本家を訪れました。震災から10年が経過し、葛尾村の避難解除後の時間が避難期間に迫ろうとしていた初夏でした。まだ日の高いうちに隼也さんが家の周りを案内してくれました。母屋の横の倉庫にはこの家の人が畑を耕しただろう農具が何本も立てかけてありました。今すぐにでも畑を耕せる道具が揃っていながら、この土地の作物は食べることがためらわれる状況にありました。避難指示解除に先立ち松本家の周りも除染が行われましたが、かげ広谷地の空間線量率は、村の中心部より高い数値を表示していました。避難解除となって暮らすことが認められたとしても、いくら基準値以下であるから安全だと説明されたとしても、目に見えない放射線の人体への影響を恐れずにはいられない状況が続いていました。
しかし、そこは死の土地ではありませんでした。庭先の斜面に咲いた花を示しながら隼也さんが教えてくれました。お祖母さんが時たま家に戻る機会があれば花を植え世話をしているそうです。野花の中に人が手入れをしている柔らかい土の一画がありました。目線を上げれば畑には野菜の代わりに草花が育ち、周囲の丘には初夏の緑が葉を重ねていました。一方で、戦後の松本家の収入を支えたタバコの乾燥小屋が自然に囲まれてがらんどうの空間を抱えていました。隼也さんが兄弟で遊んだ子どもの頃の思い出を話しながら案内してくれた裏山には、母屋に覆いかぶさりそうな勢いで草木が茂っていました。数年後の秋に訪れた際には、葛尾村で珍重されるイノハナ(香茸)と呼ばれるキノコが、何年も採る人のいない山で何株も大きく成長しているのさえ見つけました。原発から飛散した放射性物質の一つである放射性セシウム(セシウム137)は土壌や落ち葉に付着しやすく、土壌の表層近くに長くとどまります。植栽と自然が同化しつつある植物も、山間の村の生活を支えてきた山の幸も、何事もなかったかのように育っているのを目にしながら、その場所を訪れる私たちは線量の高さを考えざるを得ないのです。
 2021年6月5日の松本家の母屋横の倉庫(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日の松本家の母屋横の倉庫(全村避難から10年2ヶ月22日)
 2021年6月5日の松本家のタバコ乾燥小屋(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日の松本家のタバコ乾燥小屋(全村避難から10年2ヶ月22日)
 2021年6月5日の松本家の裏山(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日の松本家の裏山(全村避難から10年2ヶ月22日)
松本家の前庭でBBQを楽しむその日の午後の一コマを友人が写真に撮ってくれました。後日写真を見た時に、無邪気な私たちの奥に葛尾村ではめっきり見なくなったフレコンバックの山が写っていることに気がつきました。松本家の田畑に積まれたフレコンバックは単に葛尾村の辺縁部に位置し搬出が遅れていることだけを示しているのではありません。松本家の北側は浪江町南津島に接しており、そこは今でも避難指示が継続されている帰還困難区域(2025年1月18日現在)に入ります。属する町村が異なるだけで松本家とフレコンバックの仮置き場からその背後の丘まではいたって地続きです。しかしフレコンバックの置かれた休耕田畑より奥の土地はまだ除染さえ進んでいないのです。ちょうど松本家の土地を境にして居住が許されている場所と許可されていない場所が隣り合っています。いえ、かつては行政の境さえそこにはありませんでした。浪江町に合併される以前、そこは津島村の一部であり、松本家を含むかげ広谷地一帯も津島村に含まれていた時期があったからです。それゆえ、松本家の墓地はフレコンバックの背後の丘、現在帰還困難区域内(浪江町南津島)にあり、震災以降からは、行政の許可なしには墓参りができていないと聞きました。帰還困難区域は住む場所と先祖の場所を分け、松本家の中にも境界を引きました。帰還困難区域内への通行はバリケードにより封鎖されました。松本家の高台を裏手に降り仮置き場を抜けると、道路に鋼材が横たえられ、フェンスが閉じられていました。「この先帰還困難区域につき通行止め」と黄色地に赤青字で記された看板が目立ちました。周囲の山や田畑が初夏の緑に覆われている中で、立て看板とバリケードだけが人工の色合いを鮮明に主張し、それでいながら人の進入を強固に拒んでいました。
 2021年6月5日の松本家でのBBQ。後方に除染土の入ったフレコンバックの仮置き場が見える。(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日の松本家でのBBQ。後方に除染土の入ったフレコンバックの仮置き場が見える。(全村避難から10年2ヶ月22日)
 2021年6月5日、松本家の休耕田の仮置き場。中央に見える民家は浪江町南津島の帰還困難区域に属し入口がバリケードで封鎖されている。(全村避難から10年2ヶ月22日)
2021年6月5日、松本家の休耕田の仮置き場。中央に見える民家は浪江町南津島の帰還困難区域に属し入口がバリケードで封鎖されている。(全村避難から10年2ヶ月22日)
 2021年6月6日、松本家の裏の仮置き場。右後方に見える民家は松本家。(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日、松本家の裏の仮置き場。右後方に見える民家は松本家。(全村避難から10年2ヶ月23日)
 2021年6月6日、葛尾村かげ広谷地(左)と松本家墓地のある浪江町南津島(右)の境界道路。旧津島村に向かう道はバリケードで塞がれている。(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日、葛尾村かげ広谷地(左)と松本家墓地のある浪江町南津島(右)の境界道路。旧津島村に向かう道はバリケードで塞がれている。(全村避難から10年2ヶ月23日)
 2021年6月6日、松本家墓地(浪江町南津島)に入る道路上に設置されたバリケード(全村避難から10年2ヶ月23日)
2021年6月6日、松本家墓地(浪江町南津島)に入る道路上に設置されたバリケード(全村避難から10年2ヶ月23日)
私たちはこの時の経験から「松本家計画」という自主プロジェクトを始め、その後も度々松本家を訪れるようになりました。翌2022年の3月11日、震災から11年が経過した日に訪れると裏の田んぼにはもうフレコンバックが残っていませんでした。代わりにソーラーパネルが元タバコ畑の面積いっぱいに並べられていました。フレコンバックからソーラーパネルへの転換は原子力発電の負の産物から自然エネルギー発電への移行であり、復興の波が松本家にもやってきたのだとも言えましょう。それでも、私たちはあまり変化のない松本家から田畑に起きた大きな変化を見下ろして、得も言われぬちぐはぐさを感じていました。ソーラーパネルは地面に基礎を打って設置されその下を耕すことはできません。それは地面に置かれただけのフレコンバックよりも元の状態からは遠ざかっているように思えました。復興は元の状態に戻っていくことではなく、また別の状況に変化していくことなのかと腑に落ちた気にもなりました。こうして、松本家の風景にはソーラーパネルという新たな仲間が加わりました。
 2022年3月11日の松本家(全村避難から10年11ヶ月25日)
2022年3月11日の松本家(全村避難から10年11ヶ月25日)
 2022年3月11日、松本家の元タバコ畑に設置されたソーラーパネル。 (全村避難から10年11ヶ月25日)
2022年3月11日、松本家の元タバコ畑に設置されたソーラーパネル。 (全村避難から10年11ヶ月25日)
 2022年9月9日のかげ広谷地。フレコンバックが撤去された元田んぼに秋草が生えていた。(全村避難から11年5ヶ月26日)
2022年9月9日のかげ広谷地。フレコンバックが撤去された元田んぼに秋草が生えていた。(全村避難から11年5ヶ月26日)
 2022年9月9日の浪江町南津島地区帰還困難区域のバリケード。バリケードの先にある民家は植物に覆われ見えない。(全村避難から11年5ヶ月26日)
2022年9月9日の浪江町南津島地区帰還困難区域のバリケード。バリケードの先にある民家は植物に覆われ見えない。(全村避難から11年5ヶ月26日)
 2022年9月9日の浪江町南津島地区帰還困難区域のバリケードと線量計。平常時の大気空間放射線量基準値(0.23µSv/h)の約2.5倍の数値を示している。(全村避難から11年5ヶ月26日)
2022年9月9日の浪江町南津島地区帰還困難区域のバリケードと線量計。平常時の大気空間放射線量基準値(0.23µSv/h)の約2.5倍の数値を示している。(全村避難から11年5ヶ月26日)
 2022年9月9日の松本家の子ども部屋。(全村避難から11年5ヶ月26日)
2022年9月9日の松本家の子ども部屋。(全村避難から11年5ヶ月26日)
 2022年9月9日の松本家の居間にかかっていたカレンダー。家族が戻ってきた時にめくられる。(全村避難から11年5ヶ月26日)
2022年9月9日の松本家の居間にかかっていたカレンダー。家族が戻ってきた時にめくられる。(全村避難から11年5ヶ月26日)
数ヶ月や1年のうちに松本家に変化が起こることはほとんどありません。いつも季節の巡りに合わせて周りの自然だけが移り変わっていきました。フレコンバックがなくなりかつての農地に草花が生えるようになると、私たちはしばしば田園風景にうっとりとし、ここが被災地であることを忘れそうになります。しかし、松本家の裏に設置され続けている帰還困難区域のバリケードを目にした途端に現実に引き戻されるのです。バリケードのそばには線量計が置かれており、いつも村の他の場所よりも一段と高い数値を示していました。それが何よりそこが帰還困難区域である証のような気がしていました。2024年の7月末に見つけた変化は微小ながらこの場所の空気を大きく変えてしまうように思えました。バッテリーが故障したのか、もう測らなくていいとなったのか、線量計はもう何の値も表示していませんでした。作動しない線量計とバリケードによって区切られた土地はその両側に何の違いがあるのかまるでわからなくなりました。松本家自身も少しずつ変化しています。帰還困難区域に切り離されていたお墓は家族の移住先近くに移されました。まるで少し外出しているだけかのようにそのまま残されていた生活用品は少しずつ片付けられていきました。人が住んでいる家と空き家の間の松本家のグラデーションがじわりと動いています。
 2024年7月28日、かげ広谷地と浪江町南津島の境にある線量計が止まっていた。(全村避難から13年4ヶ月14日)
2024年7月28日、かげ広谷地と浪江町南津島の境にある線量計が止まっていた。(全村避難から13年4ヶ月14日)
 2024年7月28日の松本家(全村避難から13年4ヶ月14日)
2024年7月28日の松本家(全村避難から13年4ヶ月14日)
執筆:筏千丸(松本家計画)
写真撮影:松本家計画