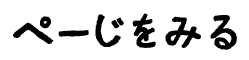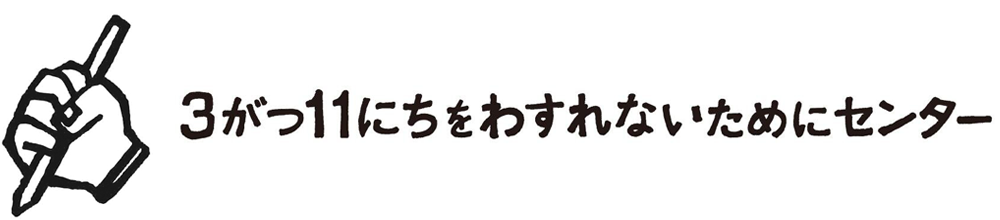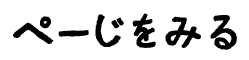

この記事は、2023年12月6日にお茶の水女子大学の授業(担当:丹羽朋子)で行った対話ワークショップの記録を、学生有志が編集しまとめたものです。
本ワークショップに参加した学生30名は、「わすれン!」に寄せられた4本の映像を視聴したのち、4グループに分かれて対話を行いました。参加者同士で映像の感想を共有し、その後「問い」について話し合いました。
このページでは、DVD『生きられる家(1)岡田地区 吉田さん宅』(撮影:佐藤貴宏)を観て、「今もなお住み続けるのはなぜ?」という問いをめぐり思索した対話の記録を掲載します。

*文中の話者A〜Gのアルファベットは、ワークショップを実施した際に着席していた席順を示しています。
『生きられる家(1)岡田地区 吉田さん宅』をめぐる対話
話者A 『生きられる家』という映像は、仙台の海沿いの地区に代々住み続けてきた吉田さんの、3つの家が全て津波による大きな被害を受けたという話でした。ぐちゃぐちゃになった家を見て、はじめは片付ける気も起きなかったけれど、ボランティアの方が家の中をきれいにしてくれたのを見て、家を直そうと決めたと話されていました。
自分も以前ボランティアに参加したことがあって、誰かに感謝されるためのものではないと思ってたけど、誰かの生活を支えることにもつながってたのかもしれないな、と思いました。
話者B 被災があった後に家を直して復旧したっていう部分がメインで、私、今まで被害の様子をニュースで見たことはあっても、そのあとがどうなったかっていうのは見たことがありませんでした。家を直すのは途方のない作業だと思うとともに、それでも住み続けようっていう意思がすごい、強いなって感じました。
あとは、高齢の方でも津波を経験したことがなくて、逃げようと言わなかったという話があって、たった100年間その地域に災害がなかっただけで、危機意識ってなくなっちゃうんだなって。世代を超えて伝えていかないと、同じようなことを繰り返してしまうと思いました。
話者C そのお話のあとに吉田さんが、「伝えていくのって難しいですね。」とおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。私は3.11の時、学校から家に帰ってきて、祖父母と一緒にテレビ中継を見ていました。祖父母も私と同じように驚いたりとか、怖いねと言ったりしていて、祖父母でさえも未経験であるということが衝撃でした。やっぱり高齢の方たちは長く生きているぶん言葉に重みがあるので、下の世代はそれを鵜呑みにしてしまう。わすれン!のスタッフの方が、3.11のときに生まれてなかった人がわすれン!の施設を訪れてくれてると話されていたのを聞いて、もうそんなに時が経ったんだと感じました。これまでは、3.11を知らない世代の人たちに言葉で伝えていこうという気持ちがなかったので、自分も震災を経験した一人として伝えていくというのは大切だな、と改めて思いました。
話者D 当時はどこにいたんですか?
話者C 埼玉県です。
話者D 壁を指しながら「ここまで波が来た。」みたいな話をしているシーンがあって。普段飲んだり、手を洗ったりしているような、生活の中にありふれたただの水が、家や壁を突き抜けてくるのとか、人間が抗えないほどの力を持つというのをあまり想像できなくて。でもたしかにここまで水が来て、家がなくなったんだというのがよくわかりました。
今は発信するためのいろんな媒体が増えているのに、伝えることの難しさはなぜ変わらずあるんだろうということは思っていて。でも、むしろ発信することのハードルが下がったことが情報を溢れさせてしまって、重みや関心を分散させてしまったのかもしれない。
あと、また津波が来るかもしれないと知りながらも、とどまり続けようと思わせるものは何だろう、土地が人を結びつけてるものは、人を離さないものは何なんだろう、というのも考えさせられました。人がその土地を思う気持ちみたいなものが気になるなと。
話者F ふるさとに住み続けようという考えが、私にはあまりないものだなと思って、印象的でした。水害が起きて家が水浸しになったら、片付けなくちゃいけないというのはなんとなく理解していましたが、全部やり遂げようとすると、何年もかかって大変なんだなと改めてわかりました。
床板をはがして、畳を張り替えて、板を張り付けて……って、一つ一つ考えると本当に途方もない作業。いざ自分がそうなったら家を手放して新しい場所に行くだろうと思うので、その地域に住み続けるというところに、人と地域のどのような結びつきがあるのだろうと思いました。吉田さんが高齢者の伝承について話していたので、先祖代々の土地だからという意識が強いのかなとも。
話者E 私は内陸の国の出身で津波は来ないので、当時はあまり馴染みのないことでした。でも今改めて津波の映像を見てみると、言葉では表せない感情になります。逆らえないじゃないですか、自然だし。
先ほど話に出た、その地域から離れられないということについては、長く住めば住むほど、その土地や人に対してさまざまな感情が生まれてくるだろうから、その気持ちはわからなくもない。私はずっと前から日本に行きたいって言ってたんですけど、親戚からは、もし日本に行ったら津波の被害に遭うかもしれないよ、と言われていました。私は元々いた土地にはあまり未練がなかったので、そこを離れてもいいと思っていたんですけど、震災が来ても離れたくないっていう強い気持ちもわかるような気がします。
話者F 土地と人とのつながり、復旧にかかる時間と手間、世代間の継承、自分がどう伝えていくかといったトピックが出てきました。
話者D なにか一つを掘り下げてみます?
話者F もし自分のいる地域が災害にあったら、動くか動かないか、とかはどうでしょうか。
話者A 私は当時も今も、千葉にいます。結局、私は土地というよりも人の方に愛着があるって思っていて。もし友達が皆いなくなったら、そこに住む意味はないかな。
でも、吉田さんの地区の場合は住民の半数ぐらいが残って、半数ぐらいは別の場所に移っていったようなので、吉田さんがとどまった決め手は周りの人ではなかったのかなと感じました。
話者B 私は東京生まれ東京育ちで、都内を転々としてきました。生まれてから10年ぐらい住んでいた場所にいた時なら迷ったかもしれないけど、今は近くに知り合いもいないし、SNSでつながることができる時代だから、離れてもいいかなと思います。
話者D なるほど。場所を変えてもSNSで人とつながることはできますね。
話者F この映像が作られたのは少し前なのかな?
話者A 2011年ですね。
話者D 当時と今とでは、人とのつながり方が変わっていそうですよね。
話者C 私は生まれも育ちも埼玉です。埼玉の田舎に住んでいて、自分の家以外にも田んぼや畑なども持っています。先祖代々、同じ土地で家を建て替えながら住み続けていて、人というよりも土地への愛着みたいなのがあるので、私だったら動けないんじゃないかなと思います。
話者D 私は愛知出身で、今は大学の近くに住んでいます。地元への想いは、だんだん変化しているような気がしていて、元々は未練がなかったんですよ。というか、だから(地元から)出てきた。けれど、いざ移動してみたら、意外と自分のアイデンティティが地元と結びついているかもしれないと気づきました。そこで育まれた何かが今の自分につながっていると思うと、地元に対する見方も変わってきますね。
話者E 私もさっき言った通り、土地に対する未練はあまりないけど、今は離れて暮らしている家族と一緒にいたいっていう気持ちがなくもない。誰の近くにいるかが大事かもしれない。でももし震災があったら、おそらく、うーん……残ると思う。「こんなことがありましたよ」って人に伝えるために。海外から来た人として、国内だけじゃなくて国外にも伝えられるようにしたいです。
——問い:地震・津波の再来に恐怖を感じながら、今もなお住み続けるのはなぜだと思いますか?
話者F 私は親の転勤の都合で、いろいろな場所を転々としてきました。今は埼玉に家族と住んでるんですけど、人とのつながりもあまりなくて、今は地元の友人とも頻繁に会うわけでもなくて、SNSのつながりで事足りるし、先祖代々の土地というわけでもない。なので、もし被災をして家を直すということになったら別の地域に移るかな、と思います。
ただ私も今、親族が近くに住んでいるんですけど、もし親戚同士で近くに住んで、助け合って暮らしているような場合だったら、その地域に住み続けるというのもあるのかなと。
話者G 私は神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜海岸のすぐそばに住んでいるので、すごく自分事として3.11の大震災を経験しました。家族の間で何度か内陸の高台に引っ越すことを考えたこともあります。私の場合は、家族に介護が必要な高齢者が2人いたので、介護との両立を考えると移住は難しいということになって、結果的に今も同じところに住んでいます。あとは、土地を購入してしまってるので、なかなか動きにくいという事情もあって。だから、被災した方々も同じようなことを考えたんじゃないかなと。
話者D 人とのつながりとか、先祖代々の土地であるとか、土地を買っているとかが関連していて、それが動きやすさを決めているということですかね。
では逆に、移動した人はどうしてその選択をしたのか、その選択を取ることができたのかということについて考えてみたいなと思ったんですけど、どうでしょう?
話者F もし住み続けることが難しいぐらいのトラウマとかがあったとしたら、地縁よりも優先されるのかな。トラウマがないとか、被害が比較的小さかった人の方が、もしかしたら住み続けようと思えたのかもしれない。
話者E もし子供のいる家庭だったら、子供を守りたいと思うんじゃないかな。子供にトラウマを与えないようにとか、将来のことを考えると思います。子供を守らなきゃいけないという気持ちが働くんじゃないでしょうか。
話者F 独身なのか、家庭に大人しかいないのか、子供もいるのか、高齢者がいるのかとかも関係しそうですね。
話者D 今後生きる年数とかも関係ありそう。
話者E 経済面から考えてみても、移住はすぐに決められるものでもない。
話者A 経済の話だと、たしか吉田さんが、建て直すのにお金がかかると話されていた気がします。建て直すのにもめちゃくちゃお金がかかるし、新たに引っ越すにしてもお金はかかるんだけど、国からの援助は少ない。
話者F やはり金銭的な余裕がないと難しいかもしれない。
話者D 建て直すにも引っ越すにもお金がかかるけど、住み続ける方を選択したってことですよね。
話者A そうですね、どちらにせよ膨大なお金がかかるっていう話だった。
話者D そこには何らかの理由が……。
話者A 強い思いがないと、住み続けられないよなって思います。
話者D 先ほどトラウマの話が出ましたが、意外と離れてしまった方が距離がとれて、忘れられるのかなっていうふうにも思います。住み続けてるってことは、常に過去を蘇らせる装置が近くにあるということにもなるのかなと。
話者A 忘れたくない、みたいなことですよね。
話者D 忘れたくないのか、忘れたいのか。移動せざるを得なかったパターンもあるかもしれない。
話者A 全部がきれいに分けられるわけじゃないってことですよね。
話者C 私の友達で、福島で被災して埼玉に引っ越してきたっていう子がいたんですけど、その子は放射能の問題で、どれだけ続くかっていうのが判断しがたかったから引っ越してきたって言っていました。それを私に打ち明けてくれた時も、たぶん誹謗中傷を受けたこともあって、すごく怯えながら慎重に告白してくれたのを覚えてます。だから引っ越しても引っ越さなくても、何らかの形で放射能に脅かされ続けるっていうか、その恐怖からは抜けられないのかもしれないと思うと、住み続けた方がいいのか、引っ越した方がいいのかって、判断が難しい。
話者D 脅かされ方が物理的なものなのか、言葉とかなのかで違うけど、いずれにしろ何らかの影響は受けるってことですよね。
話者F それについての判断は個人の価値観によると思うんですけど、もし今までいた地域にとどまるのであれば、同じような経験をした周囲の人たちと、その経験を共有しながら生きていける。そういった点で、住み続けるという選択をした人もいるのかも。
話者D ここまで聞いて思ったのが、見えないものに対する恐怖って今もあるなと。たとえばコロナとか、今はインフルエンザが流行っているし。やっぱりコロナ禍で思ったのは、どんな害があるのかとか、死ぬ可能性がどれくらいあるのかがある程度科学的にわからないと怖い。そういう見えないものやわからないものに対する恐怖に打ち勝つのってすごく難しい。その恐怖を抱えながら進み続けなきゃいけないから。
話者F 先行きが見えないまま……。
話者D たしかに、わからないことが一番怖い気がする。
話者A 今となっては震災がどういうものだったのかとか、原発事故がどういう事故だったか、コロナもどういう威力を持ってたのかとかがわかってるけど、当時はいろんな情報が錯綜していて、何を信じたらいいのか分からなかった。
この映像に出てくる方たちは、どういう気持ちで住み続けるって決めたんだろう? そういう問題に対する無視もあるかもしれない。どんな考えを持ってたのかが気になるな、と思いました。
話者E うーん、無視というか、個人的には感覚が麻痺しきっているのかなと思います。コロナも始まったばかりの時は、みんな意識して手洗いやうがいとかしてたけど、今はそこまでやらなくなってる人も多いじゃないですか。だからそれと同じように、引っ越せなくて最初は怖い思いをしてたけど、やむを得ず住み続けてたら知らぬ間に日常化しちゃって、そこまで考えなくなったのかもしれない。むしろ引っ越した人のほうが、現実から離れたぶん、急に思い出すことが多かったり、心に残ったりしてるんじゃないかなって思います。
話者F 「〇〇だから住み続けよう」「△△だから離れよう」という理由が先にあったんじゃなくて、離れるか離れないかの選択をした後で、理由を付け加えていって……みたいな感じなのかもしれない。残る選択をした人は、思い出を他の人と共有したり、日常化したりしながら生きていて、逆に離れていった人は、周りの人からいろんな目で見られるかもしれないという問題を抱えながら、それを覚悟して生きているのかも。その選択をしたことで後から問題がついてきたっていう感じなのかな。
全員 うーん……。
話者F でもその選択については、経済的なこととか、地域の縁とかもくっついてくるから、堂々巡りになるかな、と思いますけど。
話者D 決断を迫られて、そこで強く作用したのって、きっとその時に信じたものとか、経済的なこととかだったのかなって。そうですよね、一つずつ理由付けして決断しているほどの時間はなかっただろうし。私たちが決断する時だって、必ずしも一つずつ理由付けしているわけじゃないですよね。
話者F 住み続けたからこそ、恐怖を乗り越えなくちゃいけないっていう決意みたいなものが、後からはっきりとしてきた感じなのかなって。
話者D そうかもしれない。私たちからは強い意志を持って選択したように見えるけど、もしかしたら住み続けている中で意志が沸き立ってきたのかもしれないですね。
話者G 俵万智さんが、震災の1年以内に子どものために沖縄に移住したっていう話を聞いたことがある。その時に、有名人で、それなりに経済力があって、全国にいろんなネットワークを持つ自分だからこそ移住ができたみたいなことを発信されていて。移住したという選択は自分の中では正しかったと言えるかもしれないけれど、自分のような選択をできなかった人に対して何ができるだろうみたいな、罪悪感というか責任感みたいなものを感じておられたのを覚えています。
全員 (頷く)
話者B 話が戻っちゃうんですけど、なんで移住した人としなかった人がいたのかみたいな話で、津波で周りのものを全て流されちゃった後に、人間の医療は優先順位が高いけれど、動物病院とかは後回しになっちゃうんじゃないかなと思いました。ペットショップとかが近くになくなっちゃうから、ペットを飼っている人は引っ越さざるを得ないとか。
話者A 逆に移住しなきゃいけない理由があって移住する人が周りにいるからこそ、自分は残らなきゃ、みたいな気持ちにもなることもあるかな。わかんないけど。
話者D 周りが出ていっちゃうから?
話者A うーん、周りは移住しなきゃいけない強い理由があったりして、必要に迫られて移住してるから……なんだろう……。
話者F していいのか、してはいけないのか、みたいな。
話者G それ、ありますね。
話者F 自分に移住が許されているのか、許されていないのかというところで、サバイバーズ・ギルト(註:犠牲者に対して生存者がもつ罪悪感)になりがちなのかな。
話者A そう、そんな感じ。自分が残らなきゃみたいな。
話者C 私たちがここまで話してたのは「住み続ける選択をしたのはなぜか?」についてで、「今もなお住み続けているのはなぜか?」という方があまりなかった気がします。先日、仙台出身のわすれン!のスタッフの方が、震災の何年後かに仙台に戻ったという話をされてましたが、もし私が今、学校とか親の仕事の関係で、「東北に引っ越すけどどう?」と言われたとして、引っ越しを受け入れられるかなって。地震や津波の大きな被害があったという印象が強いから、やっぱり怖い。私だったら、今移住する決断はしないなと思います。復興も進んで、住んでる人も増えてきたと思うけど、今もなお住み続けているのは、やはりなんでなんだろう?
話者D 災害リスクが躊躇われる理由の一つかもしれないですね。
話者C そうですね。今住んでいる埼玉は、山もないし海もないし、安全なんですよ。だから、海の近くにもあまり住みたいとは思わなくて。山の方に住むのも、すごいなと思います。
話者D 今住んでらっしゃる環境が、そのような防災意識につながってるのかもしれないですね。
話者C 災害リスクの高い地域が地元だったら、どうなんだろうって思いますね。だから、「今もなお住み続けているのはなぜか」という点は、元々自分が住んでいた地域で何か問題があったとしても、そこに住み続けるのかというところなのかなと。
話者D 私の地元は愛知県で、南海トラフ地震のエリアなんですよね。小学生の頃から起こると言われ続けていて。地震が起きるんじゃないかなという気持ちがどこかにありながら、常に生活をしていました。東京も首都直下型地震が来るって言われていますよね。でもこういう可能性の話をどこまで生活の選択肢に取り入れるのかって、すごく難しいと思います。
話者A たしかに、他のことの方が優先されそうですもんね。
話者D そうなんですよね、やっぱり日常はずっと続くって思ってしまうから。今ある日常が選択の前提になってしまうっていうのはあるのかなって。
話者F 日常生活への愛着みたいなものが、そこに住み続ける選択をさせるのかな。それこそリスク最優先だったら、みんな“安定大陸”に引っ越したいから。
話者A そもそも日本っていう国自体が地震がたくさん起きているけど、じゃあなんで日本から出て行かないのっていう問題にもつながる。
話者D そのスケールで考えたら、わかることありそうですね。
話者A 自分も一員になってるから。
話者D 日本は災害リスクが高いと言われているけど、でもあえてEさんが日本に来て住もうと思った理由って何かあったりします?
話者E 先ほども言った通り、親戚とかには止められてはいたんですけど、日本に人は住んでいるし、私は日本に来たかったから。もちろん災害に遭う可能性はあるけど、でも逆らえないし、運命だなって思う。海外では、「仕方ない」で流せる日本人の考え方はどうかと思うという意見もあるんですけど、震災は仕方がないと思う。日本人を全員世界にばらまけるかって言われたら、それもできないし。地震が多いから、建物の造りが他の国と比べてしっかりしているし、技術もどんどん進化しているから、もしかしたらいつか震災を避けられるかもしれない。恐怖を理由に行かないでおこうとかじゃなくて、どうしたらそれを乗り越えられるかを考えて、前向きにいた方がいいんじゃないかなって思います。
話者D そうですよね、人がいなくなっちゃいますもんね。
話者C 無人島になっちゃう。
話者F 日本から移動しないっていうのは、その可能性とか、言語の壁とかが理由としてあると思います。その規模を小さくしたものが、震災があった土地から出て行かないっていうところになるのかな?
話者D そうですよね。国を越えてなかったとしても、気候が違うとか、方言が違うとか、気質が違うとか、そういう違いに触れるのって大変なことなのかもしれない。住む場所を変えるっていうのは、なかなか難しいですね。
話者F 住む国を変えるとか、住む大陸を変えるとか、そういう規模の大きい話になればなるほど、できる人は少なくなっていくと思うんですけど、隣街にとか、隣の県にっていうような小さい移住であっても、できる人やそのハードルを乗り越えられる人っていうのも限られてくるのかな。小さいハードルだけど、確かにそこにハードルはあると思う。
話者D もし2歳とかだったら、新しい土地に適応していくのは自然とできそうだけど、40歳とか、微妙な年齢だったらどうなんだろう。
話者F 仕事があったり。
話者D そう、仕事があったり、その年齢から新しいことを始めることに対する腰の重さも、人によってはあるのかもしれない。
話者F ここまでの話をまとめると、理由や意志よりも、移住をするのかしないのかという選択がまず先にあるんじゃないかということ。そして移住する/しないっていうことの前に、移住できる/できないという可能性があるんじゃないか。あとはそれに伴って自分は移住していいのか/いけないのかを考えるという問題があるというのがありました。
次に、「今もなお住み続ける」ということに関しては、どんな規模の移住であれ、年齢や地域の縁などといったハードルがあるんじゃないかという話になりました。以上です。
話者D 色々な要素があって難しいですね。今までの話を踏まえて、この問いにアンサーをするとしたら、ってことですよね。
話者A 恐怖というのが難しいなと思います。想像し難いものだから。
話者D さっき、仕方ないという話が出てきたけど、常に恐怖に怯えてたら生きられないから、ある程度折り合いのつけどころや、精神のよりどころを見出せてるのかもしれない。
映像に触れて、言葉を紡ぐ——「正解のなさ」と向き合った大学生の対話の記録
①今もなお住み続けるのはなぜ?——『生きられる家(1)岡田地区 吉田さん宅』をめぐる対話
②“よりどころ”とはどんなもの?——『石と人』をめぐる対話
③震災の当事者とは?——『過去を見直して、今を見つめる』をめぐる対話
④“弔う”ってどういうこと?——『参佰拾壱歩の道奥経 抄』をめぐる対話