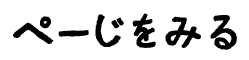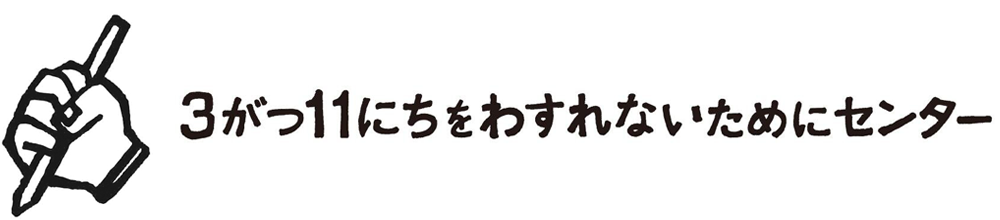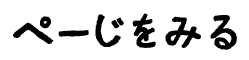

この記事は、2023年12月6日にお茶の水女子大学の授業(担当:丹羽朋子)で行った対話ワークショップの記録を、学生有志が編集しまとめたものです。
本ワークショップに参加した学生30名は、「わすれン!」に寄せられた4本の映像を視聴したのち、4グループに分かれて対話を行いました。参加者同士で映像の感想を共有し、その後「問い」について話し合いました。
このページでは、DVD『参佰拾壱歩の道奥経 抄』(制作:宙崎抽太郎)を観て、「“弔う”ってどういうこと?」という問いをめぐり思索した対話の記録を掲載します。
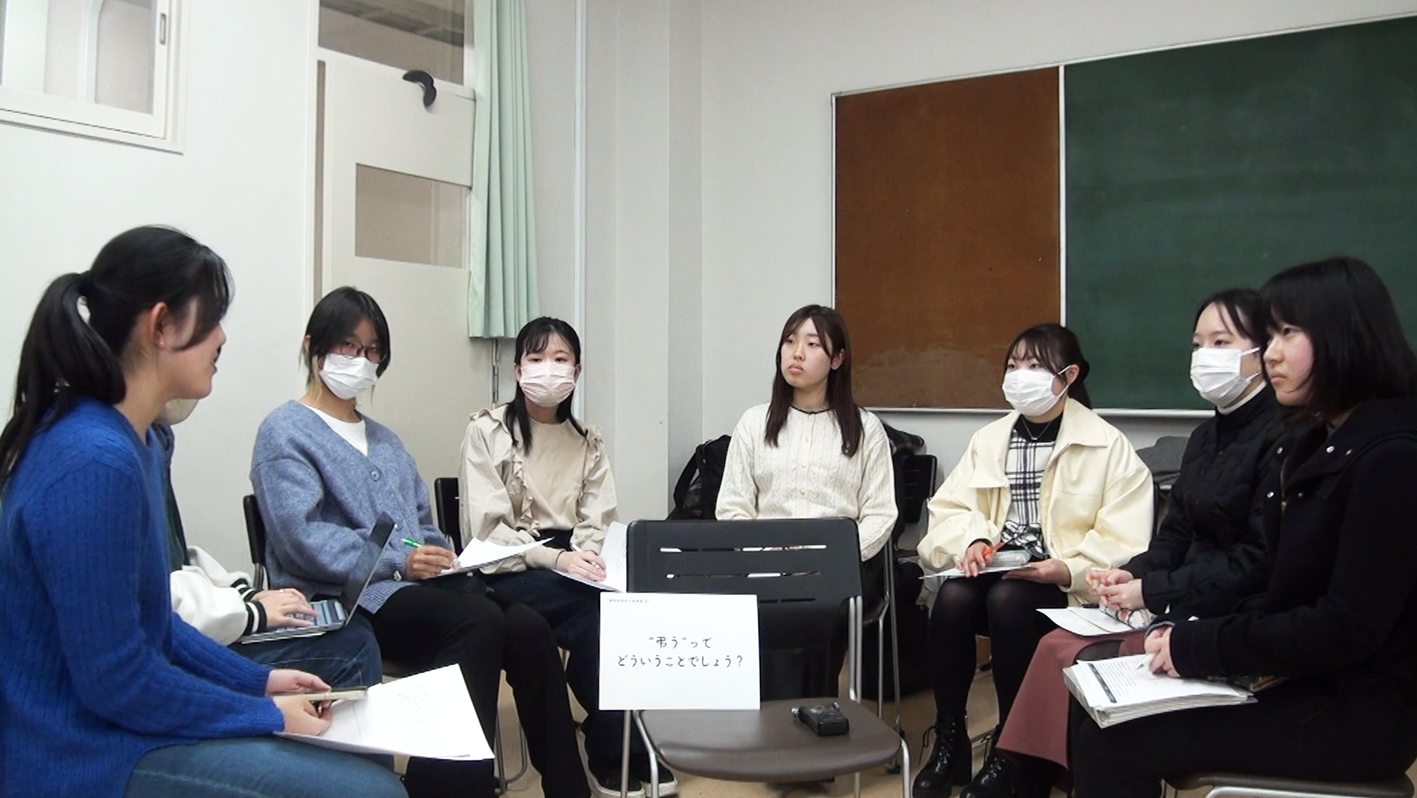
*文中の話者A〜Hのアルファベットは、ワークショップを実施した際に着席していた席順を示しています。
『参佰拾壱歩の道奥経 抄』をめぐる対話
話者D この映像を見て、淡々としたお経がずっと続いていたので、「これは何だろう?」と不思議な気持ちになりました。
あと印象に残ったのは、波が来た小学校が映っていたこと。去年、この荒浜小に行ったことがあって、映像では窓ガラスも割れてたりしてましたが、私が行った時は震災遺構になった後で、記念館みたいにすでに整備された感じだったんですね。なので、映像で見る荒浜小の姿と私の記憶の中の姿が違うなって感じました。
わすれン!のサイトの映像紹介では、制作者の宙崎さんが何でこのお経にしたかについて、「自分の肉体で感じたい」とか、「言葉にできない」と書かれてましたが、それを自分の荒浜小の記憶と重ねて「あー、すごい分かるな」とか、映像で伝わるものもあるけど、やっぱり行くことで伝わることもあるなと感じました。
話者E 宙崎さんが震災で被害を受けた地域を歩いて何を思ったのかは、「脱臼語」(註:宙崎氏による造語)なので分からなかった。というよりはむしろ、思ったことを彼自身が伏せているという方が正しいような気もしました。
震災当時に故郷から離れていたという、当事者とも非当事者とも言いがたい曖昧な立ち位置であることから、アウトプットしてマイナスな感情を吐き出したいっていう気持ちはある。だけど、何を発言するにも角が立っちゃったり、許されないような気がしてしまったりというところに共感しました。彼のお経は自分なりの奉納であって、祀りであるということですが、お経を聞いていて、震災の犠牲となってしまった方々への慰霊の意味もあると思いました。
もう一つ、阪神淡路大震災と東日本大震災の違いがスマホの浸透による情報量の増加であるという宙崎さんのお話を聞いてハッとしました。今まで私はそういう点にあまり目を向けてこなかったけれど、確実にそういうことによる被害とか、心の傷を受けた方々って、今も大勢いるんじゃないかなと思うので、今後関心をもって生きていかなければならないと思いました。
話者F 私の一番印象に残ったのもやはり、阪神淡路大震災と東日本大震災を比較して異なる点があるということでした。東日本大震災はスマホが普及したので、震災に関する情報が多くなったという話だったんですけど、今もたとえば、ウクライナの戦争や中東あたりの悲惨なニュースの映像を見ることによって、心身に影響が出てしまう方もいると思います。そういうニュースを見て、自分なりの考えを持ったり、誰かの立場になってみたりっていうのは大切なことではあるけど、ときにはニュースはニュース、という一歩引いた目で見てみるのも必要なのかなって。
宙崎さんは、情報の波があっても、タイムラグが生じてもいいから、自分の目で震災の跡を見たかったと語っていらしたんですけど、映像は震災の悲惨さとかを効果的に見せてくれるけど、そのぶん伝えられることには限りがあるとも思いました。
話者G 映像の中で「自分にベクトルを向けて作られた」というお話があったのが、すごく印象に残ってます。
というのも、震災って膨大な数の悲しみや痛みを生み出すけど、それが膨大な数すぎるとその中で序列化が起こってしまって、「自分は娘を亡くしただけ」とか「母親亡くしただけ」とか、本当はすごくつらいはずのことを「だけ」で済ましてしまう事態が起こるんだろうなって。
宙崎さんにとっては、自分の痛みとか悲しみが実感できない痛みだったことが大きかったんじゃないか。実感できれば悲しみとか涙とかで自分の中から吐き出せるけど、そうできないと、実感ができないのに現実は起こってしまっているっていう情報の錯誤に追い詰められてしまう。それがすごく苦しかったんじゃないかと思いました。
話者H 私は映像を見て、この人が紡ぐ言葉がすごい好きだなって、とっても誠実な自己表現をする人だなって、シンプルに思いました。かつ、私自身が考えていることをそのまま口にしてくれた人だなと。
私は福島県出身で、小さい頃から原発事故とか震災が近くにあったんですけど、それが当たり前すぎて、改めて考えたのが2020、2021年とか、10年ほど経ってからだったんですね。それをまさに宙崎さんがこの動画の中で、「たとえ、大遅刻であっても触れておきたかった」って言葉で表してくださって。今まで言葉に表してなかった複雑な感情を、ナレーションの部分で宙崎さんがすごく素敵な言葉でまとめてくださったのが心に残りました。
ただ一方で宙崎さんの言葉から、自分自身がサバイバーであることへの罪悪感みたいなものも感じて、宙崎さんつらいだろうなって、この動画を作った後に生きてくのが絶対つらいんじゃないかなって、共感しました。
話者A 私は最初見た時は、ナレーションが始まる前の部分では何がどういう風に、何のために動画を撮っているかわからなかった。ナレーションや説明を読んだり聞いたりして、この動画がおそらく誰かに見せるためじゃなくて、自分のために作成した動画なんだろうっていうのがわかり始めました。
悲しみを人前では表現しにくい震災という状況に対して、宙崎さんはこういう形でアウトプットしているんだと感じた一方で、私自身は撮影者の感情をアウトプットする目的で動画を撮影たり、何か記録を残したことがないなって思って。私は動画を撮るんだったらきれいな景色を撮るとか、その場で起こっていることを撮ることが多いから、すごく新鮮に感じました。
あと、非当事者といえる私が動画を見て、勝手に責められている気持ちになって、当事者でないことに罪悪感も覚えました。
話者B 私も全部通して見て、よく分からないって思ったのが率直な感想です。脱臼語っていうのもあるし、感情をアウトプットするために撮るっていうところが、本当に想像がつかないというか。どんな気持ちで撮っていたのかを考えたいなと思って、この班に来たっていうのもあります。
当事者であり非当事者でもあるというお話を聞いて、じゃあどこまでが当事者で、どこからが非当事者なんだろうって、自分自身も考えないといけないなと感じました。
話者C 私はこの動画を見た時に、何をしているのかなってところから入ったんですけど、言葉がわからなかったぶん、かえって映された景色に目がいって、とても生々しく感じられました。浴槽だけが残っている草むらだったりする景色が印象的で。
あと、この作品は距離感が絶妙だなとも、また今日の時代ならではのSNSの距離感についても考えさせられました。
私は震災当時は小学1年生で当事者でもなかったけど、当時テレビの映像だけでもとても怖くて、ずっと暗い気分になっていた程度ではあるんですが、その距離感、現地との圧倒的な隔絶みたいなもの、当事者では無いと思っているところからして、宙崎さんと同様の距離感を感じていました。
あとはその「近いのに遠い」という距離が言語化できない、そういう言葉との距離とか、時間という距離とか、すごくピッタリと噛み合っている、テーマに噛み合ったような距離のとり方だと感じて、これ以上にない形式なんじゃないかと、最終的には思いました。
話者E 私は、感情のアウトプットのために動画を撮るという宙崎さんのお気持ちを聞いて、「あ!私と全く一緒だ」と思いました。
(数名から驚きの声)
話者E だから、さっき他の方がそれが新鮮だって話されていたのが、「え!そうなんだ」って思って。今までそういうことを自分以外の人に確認したことがなかったので、みんなもそうだと思っていたんですけど、これって、自分のアイデンティティだったのか!って気づきました。
話者D え、どういう時にそれをしているんですか?
話者E うーん……マイナスな感情とか怒りの感情をもった時に、どうしてもこれをもとにして何か作りたいって気持ちが湧くことがあって。でも形に残すのがあまり上手ではないから、残したいのにうまく残せないっていう食い違いが悩みの種になったりしてい増田。
話者C 私も負の感情を抱いた時にアウトプットするっていうのが、個人的には共感できました。すごく嫌なことだったりつらいことがあった時に、何らかの形に落とし込む。それは物事を語るのとは全く違う形で、しかもそれが起こっているとかそういうことがわからないような形で残すんですけど、宙崎さんの作品のそういう感じ、脱臼語の形をとったところとかが共感できたというか。自分の技量とのズレということを話されていて、私自身もそれを痛感しているので、作り手として尊敬の念を抱きました。
話者A 私はマイナスの感情を抱いた時に言語化しちゃうと、余計つらくなっちゃうタイプ。だから、自分の負の感情と向き合うことからいつも逃げてるのかなと、思いました。
話者H 私も言霊とかを信じてるタイプで、嫌なこととかを口に出しちゃうと、本当にあったと断定されちゃう、かつ人に向かって表現したり人に相談したりすると、さらにそれが、形として残っちゃうような気がして、あんまり言わなかった。でも震災に関しては、実は高校時代、すごく長い時間をかけて宙崎さんみたいに表現活動をしていたことがあって、その時は生みの苦しみがすごくて……表現の苦しみというか。
話者G 私の場合は、嫌なこととか苦しんだこととかあった時は、メモ機能に全部バーって打ち込むか、あとは寝るかっていう二択で。書き起こすと客観視できて、相手の立場になって考えられたり、逆に自分は今どういう状況に置かれて、なんで自分はこんなに悲しい気持ちになったんだろうっていうのがわかるから。それは自分の中で、「自分事じゃないこと」として片付けられる方法でもあって。
でも逆に、それが本当に現実にあったとか、客観視することで現実化してしまうのかなって思うと、表現によって苦しみが増加するか緩和するかに分かれるのは納得できると思いました。
話者D 宙崎さんや他の皆さんみたいに、嫌なことがあったときに表現したり言語化したりして、そのことに向き合うっていう方法をとっていらっしゃる方がいるのに対して、私はどちらかというと現実逃避することをとっちゃいがちなので、ちゃんと向き合うという選択をされているのがすごいと思いました。
——問い:“弔う”ってどういうことでしょう?
話者D 「弔う」って、すごい重いテーマだと思うんですけれど……。
全員 (沈黙)
話者D 「弔う」って、亡くなった人にしか使わないですよね。私がぱっと思ったのは、「考え続ける」とかかな。
話者G 私は「弔う」って「成仏することを助ける」っていうイメージだと思っていて、「自分の感情を弔う」だったら、自分の中で、自分がどうやったらこの状況を乗り切れるのかっていうのと向き合って、たとえば映像の制作者だったら映像に表すっていうのが、「弔う」の形だと思いました。
話者H 私は、「弔う」を「飼いならすこと」だと思っていて、自分の苦しさとか悲しさとかっていう感情を、消化するっていうより、飼いならすことができる状態なんじゃないかと思います。
話者E 亡くなった人に使うときの「弔う」は、たとえば「何回忌」とかで何かを残しておく、その人のかけらを心の中に残しておくみたいなイメージが強い。
話者D 「忘れない」みたいな感じですかね。
話者A 私は「考え続ける」がいちばん近いと思ってます。人生であんまり近い人を亡くした経験がなくて、震災とかどこか遠くで起きてることによって亡くなった方々に対してしか、「弔う」っていう感情を抱いたことがなくて。そうなると、その事故の原因を理解するとか、その事故の存在を記憶しておくみたいなところで、自分の理解というか、「弔う」という感情が止まってしまっていて。自分の感情が「弔う」という言葉に対してまだ乗り切っていないというか……。
話者B 私は、「無かったことにしない」ことなのかなと思っていて、たとえば誰かを亡くした時にその人がいなかったことにしない、いたことを自分の中でとっておくみたいな部分があると思うし、震災みたいな出来事に関しても、それが起きたことを風化させていかないというところで、「弔う」という使い方ができるのかなと。
話者C 「弔う」って、亡くなった人についてはどうしても一方的になってしまう。「亡くなった方々のために弔う」と言っても、相手の意見を聞くこととか、何をしてほしいかは想像するしかないし、そもそも想像すること自体が少し傲慢なのかもしれないとも思う。一方的である、というのをふまえた上で、自分たちの中に存在するその人たちを「弔う」という面を無視することはできない。
「飼いならす」ということには、その人たちがいたということを忘れないでいるっていう面と、とはいえ自分たちは今後も生きていかなくてはいけないということの矛盾する両面がある。常に忘れられないと思い続けることはなくても、いつでも思い出すことができるように、相反することを抱え続けることが、弔うことなのかな、と思います。
話者H 「弔う」っていう言葉の一部には、「諦める」という言葉が含まれていて、「弔えない」は「諦められない」と少し近い気がするんですよね。
「弔う」っていう言葉は、ある人にとっては美しい言葉でもなんでもなくって、たとえば震災から12年経っても亡くなった娘さんの骨を毎朝探している人がいたとして、その人はずっと娘の死を諦められない、受け入れられない状態だというのが、「弔えない」という言葉につながっているような気がします。
話者F 「弔う」についてこれまで考えたことがなかったんですけど、皆さんの話を聞いていて、それは亡くなってしまった方に向けての言葉であると同時に、残された人がその人の死を受け入れることなのかな、と。。さっきの「諦める」っていう言葉を聞いて、受け入れるっていうのは、その人が死んでいると諦める、っていうことなんだと思いました。
全員 (沈黙)
話者A 私、実感できてないこともあって、自分が「弔う」っていう言葉をきれいな言葉として捉えていたと気づきました。
話者D たしかに、「弔う」ってすぐには思えないというか、宙崎さんのように振り返って、過去の現実として受け入れてからじゃないと、って思いました。
話者H とは言いつつも、「弔う」って美しくもあると思っていて、なぜかというと、「弔う」って当事者と非当事者をつなげるものでもあるから。たとえば、震災を実感をすることって、非当事者にとっては難しいことだけど、弔うことならできると思うんです。3.11になったら日本全国のみんなが弔うことができるっていうのは、ある意味で救いだと思っていて、みんなが弔うことができる、人と人をつなげるという意味では、すごくいい言葉だなと思います。
話者A いいこと言う!
話者G 話を聞いているうちに、最初は「弔う」って、亡くなった人のためにあることだと思ってたけれど、残された者のためにある言葉だとも思うようになりました。振り返ってみると、たしかに私も祖母を亡くした時、葬式の最中とかに、おばあちゃんのために頑張って言葉を言おうとか、お棺に物を入れようって思ったけど、それって自分の中で、おばあちゃんに最後にこれしてあげたい、あれしてあげたい、そうすることで自分の気持ちを整理したい、っていう気持ちがあって。だから、自分の中ではおばあちゃんのことを弔ってたつもりでいたけど、それによって自分が救われたんだなと。弔うことが残された者の救いになるって聞いて、そのことを思い出しました。
話者E そもそも、人間っていうのは他者との関わりの中に生きている存在だから、他者の中に生きているって常に思っていて。結局、自分が死んじゃったら、自分には何も残らないけれど、他者の中には残り続ける。だから「弔う」っていうのは、他者の中に生きている自分を確認してもらう作業だと思いました。
話者D そう考えると、やっぱり宙崎さんにとっては、あのお経も弔う行為なのかな。「お経」とか「まわる」というのを通じて、亡くなった人のための慰霊でもありつつ、自分が行けなかったことへの整理という面もあるのかもしれない。
全員 (長い沈黙)
話者D さっきの当事者と非当事者の話が興味深かったんですけど、当事者と非当事者で弔い方に違いがあるのか、それとも同じというか、逆に関係なく人それぞれなのか、どなたか意見ありますか?
話者A 非当事者が弔うことって簡単というか、あまり重い覚悟というものがなくともできるのではないかなと、皆さんの話を聞いて思いました。
話者E 結構センシティブな話になっちゃうんですけど、たとえば交通事故で亡くなった方がいて、その事故現場の近くにはたくさんのお花やお供え物が置いてあったり、その事故に遭った方のことは全く知らないけど手を合わせてる方がいらっしゃる。そういうのを見るたびに、「弔い」ってどういう関係性のうちに築かれるものなんだろうと思って。関係が希薄な中での「弔い」って、どういう意味合いを持つんでしょう?
震災だと規模が大きすぎるからか、そういうのはあまり感じないけど、事故での弔いってなんか難しいなって。無責任な弔いになっちゃわないかとか、思ったりします。
話者H そういう時の「弔い」は、感情で人が動くような気がする。直接その人を知らなくても「かわいそう」みたいな感情でその人を弔うことは可能……そう考えると、逆にすごく残酷なことだけど、弔うに値しないような人っていうのもたぶんこの世にいると見なされているんじゃないかって。
たとえば、自爆テロで死んだ人とか、犯罪を犯しながら死んだ人って、死んだこと自体は交通事故で亡くなった方と変わらないのに、弔われない人生、弔われないタイプにカテゴライズされてしまう……。「弔う」という言葉って、自由で普遍的でみんなできるし、されるものだと思っていたけれど、実はすごく限定的な言葉、行為なのかもしれない。
話者A 「自分自身を弔う」ってできると思います?
話者G 自分自身か……。
話者A 「他者からは弔われない」とされている人にとって、最期に弔うのは自分だけかなって思うと、それってはたしてできるのかな?
話者G 他の人から弔われないっていうのは、その人を弔ってしまうと、その人によって命を落とした人たちを弔えなくなってしまうことへとつながるから、弔われないのかも。
話者E 「弔う」の範囲は本来広いはずなのに、かえって限定的になっちゃう矛盾があるんですかね。
話者H やっぱり倫理観とかに関わってくるのかな……。
話者C さっき、「受け入れる」とか「諦める」「諦められない」という話があったけど、関係が遠くなればなるほど「受け入れる」という過程がうすくなるというか、そうする必要がなくなってしまうというか。
関係が希薄な中で、自らが弔おうとする感情が生まれるときに、同情が憐みみたいなものにすり替わるのが、私はすごく怖い。それは一方的で傲慢なことだから、そこをどのようにして当事者に寄り添う形にできるのかというのが、感情がとても利己的なものであるがゆえに難しいなと思う。
話者G たとえば事故とかでは、メディアの発信の仕方でも変わるのかな。亡くなった方単体で見ると、その人が亡くなったことをかわいそうだと感じると思うんです。
でも、もし亡くなった子のお母さんがいて、お父さんもいて……みたいな時には、子どもを持つ親って絶対つらい状況だから、そのニュースを見た人は、残された親の方の感情に寄り添う時間をもつこともあり得る。だから、どういう風にその状況を伝えられたかによって、「弔う」っていう言葉のあり方も左右されるのかなって思いました。
全員 (沈黙)
話者A 同情することで自分の中に生まれる負の感情とか、かわいそうっていう感情を向けることが傲慢なことはよくわかる。でも一方で、感情を向ける先が「弔う」っていう形でなかったとしたら、それはそれでかなりしんどいなって思うから、「弔う」の範囲を絞らない、関係者を絞らない形をとることこそが「弔う」の価値だとも思うんですが……。
話者D 3.11については、今も毎年テレビで中継して黙祷とかするけど、そのときに自分がどういう感情で黙祷しているかな、と思って。たしかに「かわいそう」とか、同情的な感情もあると思うんですけど、そういう風に「弔う」っていう行為が広く行なわれることで、毎回思い出させるとか、知らない世代も知るきっかけになるという面もある。ここまでは個人が弔う話をしてきたけど、そういう何周年のように広く行なうことは意味があることだと思いました。
話者G 戦争や震災、事故の話とかを聞いた時に、自分の中で自分の感情を介してしまうことが申し訳ないように感じてしまうのが、すごく難しい。その当事者の方たちしか理解できないことがあるのに、それに対して自分の中で表面的に感情化してしまうことで、その人たちを傷つけるやり方になってしまう気がして。
だからこそ黙祷とか、小学校の頃から何度もやってきたけど、そのたびに自分が弔っているつもりになっているのがすごく怖くて、しかもそれが日常化して儀式化してしまってっていうのがあって。どういう風に向き合えばいいんだろう? どういう感情でいればいいのか分からないし、どういう風に自分が非当事者として向き合えばいいのかもわからない……。
全員 (沈黙)
話者H 最近、「弔う」ってしました? 日常的な言葉じゃないですよね?
話者E おじいちゃんの七回忌でやりはしたんですけど、もう七回忌だから、本当に悲しかったお通夜の時の悲しさっていうよりは、亡くなってしまったのを受け入れてはいるので、「おじいちゃんいたなあ」「あの時、あの話したなあ」っていう社会的な営み、親族の人たちと会って話す、それこそ儀式的な感じですね。
話者A 10月頃、ガザで起きてることを知るセミナーにオンライン参加した時、「はじめにみんなで黙祷の時間を取りましょう」って言われてやったのが直近の記憶かな。その時の自分はどうだったかなっていうと、感情に寄り添うっていうよりは、知識として今ガザで何が起きているのかとか、ニュースで見た出来事とかが頭の中でぐるぐるしていて、あんまり心を使って弔ったっていうより、わりと頭を、知識とかを整理する時間になっちゃってたかな。
映像に触れて、言葉を紡ぐ——「正解のなさ」と向き合った大学生の対話の記録
①今もなお住み続けるのはなぜ?——『生きられる家(1)岡田地区 吉田さん宅』をめぐる対話
②“よりどころ”とはどんなもの?——『石と人』をめぐる対話
③震災の当事者とは?——『過去を見直して、今を見つめる』をめぐる対話
④“弔う”ってどういうこと?——『参佰拾壱歩の道奥経 抄』をめぐる対話