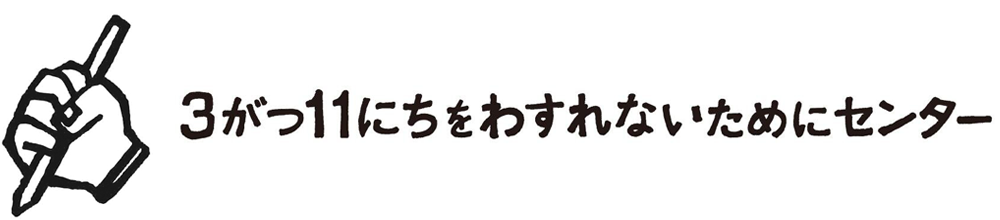![]()
2013年11月30日
楽しく学び、遊んでいた、大好きな大川小学校でたくさんの子どもが犠牲になりました。
あの日から私たちはずっと考えています。
子どもたちの小さな命が問いかけているものはなんだろうと。
遺族はもちろん、関心を持っている方すべて
市教委や検証委員会のみなさんも
ずっと考えているのだと思います。
小さな命の問いかける意味は、深く、重い。それに向き合いたいと思います。
何をいつまで、と思うかもしれません。その通りです。時間はどんどん過ぎていくのですから。
警報が鳴り響く寒い校庭で、子どもたちは危険を察し、逃げたがっていて、
それでも先生を信じて、指示をじっと待っていました。
その事実から目を背けてはいけないと思います。
あの日の校庭に目を凝らすことで、何か大切なことが見えてくるはずです。
悲しみは消えることはありません。でも、この悲しみはあの子たちの存在そのものです。 忘れる必要も、乗り越える必要もなく、いつもそばに感じていていいのだと思います。
あの日の校庭もそうでした。多くの人が、このままではいけないと感じています。 誰かが「そっちに行くな」と声をあげなければ。津波が来てからでは遅いのです。 そう考え、このタイミングで会を作りました。
趣旨をご理解いただければと思います。
2013.11.30 小さな命の意味を考える会 代表 佐藤敏郎
*「小さな命の意味を考える会」は、現在(2024年6月以降)はありません。
|
あとがたり この会を立ち上げウェブサイトでの発信を始めた頃、私はまだ中学校の教員をしていました。今振り返ると、仕事の後に、大川小学校のことを調べ、ウェブサイトに文章を書いていたことを思い出します。 2013年11月30日は、大川小学校事故検証委員会の第7回が開かれた日でした。この日、委員からの提案によって、初めて「遺族との意見交換」の時間が設けられました。 検証委員会の後には毎回、報道機関による取材対応もありました。それまでは、「遺族の有志」や「遺族の一部」のコメントとして新聞記事などに載っていたのですが、そうではなく「〇〇の会の佐藤敏郎」として発信したほうが良いのではないか、と思いはじめました。 そこで、この「小さな命の意味を考える会」をつくりました。 当時書いていたように、大川小学校の校庭で起きたことや、子どもたちの小さな命が問いかけていることを多くの人と共有したいと思い、この会を立ち上げました。 会のウェブサイトに書いてきた文章の一部は、「小さな命の意味を考える」という冊子にまとめ、各所で配布し、ウェブ上でも公開しています。 2024年からは、このウェブサイトをはじめさまざまな媒体で書いてきた言葉や写真を今一度読み直し、現在の視点や考えも織り込みながら整理し、残すための活動を進めています。 |
参考:佐藤敏郎のブログ「これまで、ここから~大川小学校のこと」
https://korekoko.blogspot.com/