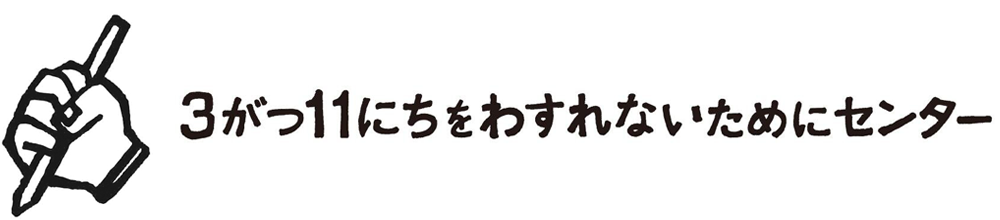University of Tsukuba assistant professor of photomedia. Research expertise in history and practice of rephotography. Trying to keep time in mind. 筑波大…
This is Doyoung from S.Korea. Media activist. So, I'll send information to Korea independent media for NEWS cham and KOREA media activist network.
震災後の日本と私達。日本に対する想いや考え。様々な行動や出来事によって起こる「社会の動きと心の動き」、その波動を感じるために活動していきます。「うちがわとそとがわ」のそれぞれの視点からの問いかけと表現は、私達自身の輪郭が放つ光を捉えようとするための試みです。インタビューでは、日本国内同様、日本国外に…
仙台でレズビアン・バイセクシャルなど「女を愛する女」の交流会やフリーペーパーの発行などをしています。東日本大震災では多くのセクシャルマイノリティも被災しました。その体験を記録・発信することによってみんなが暮らしやすい社会づくりにつなげていきたいと思っています。
福島県大玉村で、震災後の休耕地を活用した藍づくりを行う、歓藍社(かんらんしゃ)の一員として活動しています。東京と東北、都市と農村を行き来する中で目に留まる、「暮らしの創意工夫」や「手入れ」、人々が自分の手を動かしてものを直したり衣服を繕ったりする「小さな修繕・修復」の記録を行います。
コマプレスは「小さな声、低い視線」をモットーに設立、在日コミュニティや民族教育を主に取材しています。東北の民族学校(ウリハッキョ)に寄り添い、ハッキョを中心にした在日コミュニティの現在、全壊した学校の再建過程、課題などを、ありのまま、記録し伝えてゆきたいと思います。
誰でも気軽に映像が撮れるようになったことで、映像のアーカイブのあり方も変化しつつあると思います。単発的ではなく地道な継続的活動によっての「復興」の過程を長期・継続的に「記録」していくことで、後世に受け継ぐべき「記憶」を遺していけたらと考えています。
「ワシントン大学翻訳プロジェクト」 はシアトル市にあるワシントン大学アジア言語文学学科の准教授ジャスティン・ジェスティが担当する上級日本語の学生達チームが行うプロジェクトで、毎年1回和英訳授業を開き、部分的にセンターが集める証言を英訳することによって貢献することを目的としています。
被災地でのボランティア状況や観光情報を直接現地を訪問して収集しています。その被災地情報をボランティアツアーや学習プログラムを企画する資料として、旅行会社や学校へ発信してます。私たちは被災地から「来てほしい」と「行きたい」の声をつなぐ橋渡し存在になりたいと考えています。
あの震災の被害を受けた方々のその時の気持ちと動いて行く今の気持ちを記録したいと思います。 撮影していく過程で、手を出し足を出しいっしょに汗を流し、その気持ちに寄り添って行ければと思っています。
2013年より屋根裏ハイツという劇団を主宰し、作・演出をしています。作品をつくっていくなかで、出演者自身に対して、または出演者とともに、リサーチをおこなうことも多くあります。そうしてプロセスを経て生まれた作品を成果物として収めることができればと思います。東日本大震災を題材にした作品『とおくはちかい』…
ロンドンでドキュメンタリフィルム制作の手ほどきを受けました。外部から仙台へ働きにやってきた者の目で、仙台出身の一人の友人を道案内に、彼の行く先で映る文化財、街の過去と未来、そこに表れる音楽や言葉を撮っていきたいと思います。
東日本大震災により被災された方々から、発災直後からどのような体験をし、行動をとったか、そしてどのような想いを抱えたかを聞き取り、文章として残す事業に取り組んでいます。そのことで震災を風化させることなく後世へと語り継ぐことができればと考えています。
宮城県女川町に学生時代から一般社団法人対話工房を通して関わっていた、美術作家である寺嶋剣吾、今尾拓真が映像の記録/再生という手法をベースに女川町をはじめとした被災地に関わる方法について模索する活動を予定しています。
障がいがある人たちが日ごろから抱えている様々なバリアは、今回の震災でより深層化、顕在化しました。障がいを持つ方々やそれを支える方々とともに「本当のノーマライゼーション」とは何かを考えます。
震災を機に、私たちの普段の生活がどのように成り立っているのか、ということについて考えるようになりました。核燃サイクルに反対する市民活動のフィールド調査を行いつつ、この先どのような生活の復旧・復興があるのかを考え、記録をすることでいろいろな人に関わっていきたいと思っています。
利府町在住の佐々木と申します。3.11前後の利府町の記録が、災害ボランティアを通じて得た情報・記録などを皆さんと共有していきたいと思います。私的な思いとしては、3.11から失ったもの・逆に得たものを忘れず、生きている「いま」に感謝しながら活動したいです。
高校生の震災映像ワークショップを高校生と目線が近い大学生という立場からお手伝いさせていただきたいと思っています。高校生たちが震災と向き合う際に生まれるであろう迷いなどを高校生に寄りそう形で支援していけたらと思っています。
仙台市若林区荒浜に、震災前に存在した市営バス停留所を模したオブジェ「偽バス停」をつくって設置しています。2016年12月11日、「3.11オモイデツアー」とのコラボ企画となる「きょうは市バスに乗って、荒浜へ」を実施。現在おやすみ中の終点・深沼停留所に、1日だけですがバス来ました。
今回の震災に関して学生も様々な活動や取り組みを復興のために行っており、また学生自身も震災を体験し、そういった一人ひとりの持っている証言や活動を多くの人に発信したいと思っています。学生の活動を伝える手段を作りたいと考えています。
津波による甚大な被害を受けた山元町。震災直後から山元町役場の災害対策本部・避難所の様子をビデオカメラで記録してきました。発災時、災害対策本部がどのように動いていたか、そして、避難した方々にどのように情報が伝達されていったのか。あの日、皆が奮闘していた記録を伝えていきます。
女川福幸丸は女川が大好きで女川のために何かしたいという気持ちだけで集まった若者達の団体です。団体名には「女川の福幸(復興)に向かって船出しよう」という意味がこめられています。昨年10月に開催した音楽イベント「我歴stock」を皮切りに、これからも女川のためにできることを模索します!
東日本大震災により家族(祖母、母、妹)を失い、命の偉大さを感じ、伝統の復活・継承(陸前高田うごく七夕まつり森前組)や伝統の創造などやるべき事を遂行しています。様々な表現を様々な切り口で輪を作り出し、地元である陸前高田を軸にクリエイティブな聖地構築を志します。
石巻市大川小学校では、東日本大震災で多くの児童・教職員が犠牲になりました。深い悲しみに沈んだこの場所に連日多くの方が足を運びます。大川伝承の会では、あの日の事実に向き合い、何を伝え、どう遺していくか試行錯誤を続けています。その中で累積してきた考察、想いを様々な言葉や手法で展示(格納)します。
東北から発信される演劇を知り、そこで生きる人々と関わる。演劇が社会に対して持つ力を再発見する。そこで出会ったもの、人々の姿を言葉にし、論文にすることで整理し、残し、伝える。加藤さんとともに活動。
市民からご提供いただいた震災画像を集めてWebにアップしています。画像提供者より、撮影時についてヒアリングを行い、テキストアーカイブできればと考えています。平成28年度より「NPO法人20世紀アーカイブ仙台」から「3.11オモイデアーカイブ」へ震災アーカイブプロジェクトを移管。
インドや諸外国を舞台に、工作を通じて大地と技術と人間の関係、在るべき生活風景を探求する国際建築学校In-Field Studioを主宰しています。その実践作業の記録を介して現地の人々の生活の内実を探りたいと思っています。また福島県大玉村で藍づくりを行う歓藍社とも密に接続させます。
ボランティアで出会った石巻のカフェ・ギャラリーを甦らせます。漆喰という素材で下地から壁を塗ります。復旧し使用できるようになるまでの期間の中で、出会った石巻の方の声・街の様子・暮らしを記録していきます。また他の方の石巻を知るきっかけ、現地の方の憩いの場、安心できる場所をつくります。
学生時代から福島県双葉郡葛尾村に通っています。避難者と移住者の割合が多くなった地域社会、そして人に住まれなくなった家や集落のこれからに関心があります。本業はソフトウェアエンジニアです。
宮城県亘理郡山元町で『思い出サルベージアルバム・オンライン』という被災写真の洗浄・デジタル化のプロジェクトを行っております。この「思い出サルベージ」についての情報発信、ボランティアの募集、他自治体で写真洗浄を行っている組織とのネットワーク化を考えております。
初めまして。震災がもたらした様々な影響の中で、私がとりわけ気掛かりなのは、子どもたちの教育への影響と、職やつながりを失ってしまった人々です。微力ではありますが、その人たちの声を多くの人に、地域や時代を超えて伝える一助になりたいです!!
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いを生の声で記録し、被災地の復興の現状をホンネで話し合う番組を、Ustreamで配信します。 震災以降、自分のできることは何かを繰り返し自問しながら、このリアルふっこうボイスに携わっています。
自由の森学園高校で実施している選択授業「東北と復興」メンバーが、1年間の授業の中で学び考えたことの記録をアーカイブしていきます。埼玉の高校生が実際に東北の地を訪れ、見て聞いて考えた復興についての記録を次世代につなぎます。
女川の皆さんと共に活動しています。災害は日々の暮らしの中にあった身近な存在や、自然との対話の大切さに気づかせてくれました。「表現と対話」の場づくりを住民と共に考え、体験しながら、住民自らの目で故郷を見直し、居場所をつくり、新しい日常を踏み出すためのお手伝いをしています。
住んでいる丸森町での地域活動や、職場のある山元町での活動を、なるべく素のまま撮影・記録したいと思っています。特に宮城県での原発による被害の記憶は、このままでは急速に薄れてしまうのでは、と心配しています。
宮城野区の方々に対する震災の記憶や思いを記録します。ひとは過去に戻ることはできませんが、未来に伝えることはできます。活動を通して、人々の思いを残していきたいと思っています。
震災後に生まれたさまざまな表現活動や、芸術文化による支援活動について知り、そこに関わる方たちとひとりひとりの声を聞き、記録していきたい。また、そのようなアートやアーティストの活動をサポートしていきたい。佐藤文子さんとともに活動。
新潟大学人文学部北村順生ゼミ(基礎演習)では、地域間の交流授業「ローカルの不思議」プロジェクトを行っています。今回は、被災地の外側の地域も含めて、それぞれの地域において震災はどの様な関係性を持っているのか、受け止め方の違いはどのように生じているのかを、考え直していくつもりです。
震災からもうすぐ一年。5年後も10年後もこどもたちが健やかに育つことを願って。パパやママ、おじいちゃんやおばあちゃんもこどもたちのためにできることを見つけよう!笑顔で毎日を楽しむために、皆でつながり、一緒に考えていきましょう。この時代に親たちが何を考え行動しているのか発信する。
五年前より地域防災に力を入れ様々な地域防災に取り組んで参りました。3月11日にはスムーズな避難・指定避難所開設・運営ができました。地域の取り組みと災害への備を全国の皆様へ応援したいとの思いから、YY防災ネットを作り、防災応援プロジェクトを立ち上げました。
東日本大震災の直後からたくさんの映像に触れ、いろいろ感じること、考えることがありました。それを自分の中に留めておくのではなく、映像を見て人と話したり、誰かの声に耳を傾けながら、震災後を生きる人々の声を記録していきたいと思っています。
東日本大震災の瞬間、多くの人が仕事をしていた中で、それぞれの立場でどんな行動をとったのか。心の中では家族のことが気になっていたかもしれない。半年を過ぎて、ひととして色んな側面を持つ働き盛りの世代に自分を振り返ってもらい、色んな「自分」を感じてもらえる記録を作ります。
学内で東日本大震災のドキュメンタリーチームを立ち上げ、この未曾有の大震災を後世に残すべく映像として記録する。実際に震災を体験した人々が目にしたのは何だったのか。そしてその時何を感じたのか。時間の経過に対して変化するものは何か。後世でもそれを考える機会を作りたい。
東北地方を旅する中で、わすれン!と出会いました。震災を経験したのは6歳のころ。大学で身につけたデータ分析の技術や、趣味で学んでいるライターとしての知見を生かし、「3.11を記憶する最後の世代」にならぬよう、これからの世代へとつなぐ活動に貢献したいと考えています。
東日本大震災により甚大な被害を受けた中野小学校区の復興を考える地域団体であった、旧中野小学校区復興委員会のメンバーで構成している「なかの伝承の丘保存会」。その活動のひとつとして、震災と中野小学校区のことを残し、伝えるための映像記録制作を行います。ばらばらになった住民との橋渡しを行いつつ「ふるさと」を…
私は、故郷石巻を中心として、他団体の方々と協力し「懐かしい記憶の中の風景」等を共有しながら311で失ってしまった「あの頃」の姿を、地元の人、そうではない人などの希望する全ての人達に繋いで行くことを目的とした活動を続けていきたいと考えています。
仙台定禅寺通でビッグイシューを販売する鈴木太氏と仙台市在住の門脇篤氏がお送りするネット中継「定禅寺ジャーナル ウェブ版」に参加します。あなたも参加できます!毎回テーマを設定しつつも脱線しまくりの105分。もちろんUSTREAMでもご鑑賞いただけます。レッツ・ディベート!
仙台、東京、海外の多様な学生が集まり、読者が震災の体験談をサイトに投稿できる参加型ウェブサイトを運営しています。今まで語る場を持たなかった人のためが自らの思いを発信する機会づくり、東北の今を伝える記事やPodcastを通じて10年間の歩みと東北の魅力を再認識してもらう活動です。
被災地を取材している方と交流する機会を設けることによって、取材する側の葛藤や苦悩、喜びなどを共有したい。また、情報交換をすることによって取材の際にお互いに何らかの協力体制を築くこともできれば有難い。
故郷・仙台が311に見舞われつつ現地に入りしたのが4年半後の2015年9月だった。残されていたのは更地。ボランティアをするわけでもなく、なすすべもなく「ただ歩く≒只管打歩(しかんたほ)」しかなかった。その際、撮影した素材に「脱臼語≒言葉にならない言葉≒自作経」をつけてまとめます。
今回の大震災を後世の人々にどのように伝えていくのか。マスメディアによる報道だけではなく、物語という形によって後世に残していく可能性を探っていきたい。東北にある物語や民話を改めて聞く(読む)ことが東北の歴史を知り、未来を考えることに繋がるのか。そのような考えの基、活動します。
京都から被災地支援を考えるSocial Kitchen Working Groupは「女川curry & films」と題したプロジェクトを開始しました。「女川カレー」から始まった女川町との縁。一地域に特化した継続的な映像発信により、今なお続く震災と、前を向く人の姿を伝えます。
新潟県中越地震の被災地での活動をきっかけに、明るい未来を描くことが難しい時代、社会の災害復興について実践的な研究を行ってきました。被災者の人に災害から今までの気持ちを曲線で表して語ってもらう復興曲線インタビューや、震災について短文で表現する「3.11からの独り言」などをすすめています。
宮城県女川町に学生時代から一般社団法人対話工房を通して関わっていた、美術作家である寺嶋剣吾、今尾拓真が映像の記録/再生という手法をベースに女川町をはじめとした被災地に関わる方法について模索する活動を予定しています。
深く沈みこんだ記憶を、草の根から構築していく。そのためのききとりを、ゆっくりじっくりやっていきたいと思います。結論を急がずに、現実のなかにじっと身を沈めながら、私たちが何を知るべきかそれ自体を探索していくつもりで、わかりやすいスローガンに隠れがちな経験をすくいとっていきたいです。
震災を記録することの意義について追及しようと考えています。被災地の様子の記録や、記録活動に携わる人々とのかかわりを通じてどのような記録を残すべきか、どのように活かすことができるか、探っていきたいです。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
愛知淑徳大学メディアプロデュ―ス学部小川ゼミです。対話と表現をめぐるデジタル、ストーリーテリングの手法や映像制作で、地域に埋もれている声を掘りおこし、地域で共有する活動をしています。メディア、コンテ、ローカルの不思議プロジェクトも行っています。
3.11を、後世に残し、伝え続けるための活動をしていきます。震災直後の写真と同場所が今後どう変化していくのか。または変化していないのか。それを写真に撮り、残し、伝えて行く。という「定点観測」を中心に活動していきます。
東北に今いる方たちに会いに行くこと、その方たちのことばを残し、伝えることができたらと思い瀬尾なつみと活動しています。これまでもたくさんの方にお会いしお話を聞いてきましたが、そんな方々のことばや姿には色んなものが詰まっている気がします。その姿を映像で残したいと思っています。
社会で見えない存在の1つであるセクシャルマイノリティ。発災時に遠くの仲間から心配されたが「これが必要」と明確に発信できず「セクシャリティどころではなかった」現実が、今になって悔しい。みんながどう感じていたか、それを多様なままに個別に集積し仲間に役立てて欲しいと思っています。
「みやぎくらしの語り文庫」は、生活誌の口述資料「くらしの語り」を人とくらしの肉声として記録資料化して地域の人々の手の届く場に蓄え、世代を継いで手渡され、新しい創造に活用されうる「声の資料館」としてのしくみを構築し、そこに生活文化を担った「くらしの語り」を集積していくことを目指す。
蒲生の方々の協力と3.11オモイデツアーからの写真提供を受け、「故郷を語る」という聞き取りイベントを開催することで、貞山運河・船だまり・お蔵跡の歴史を住民目線で掘り起こし、蒲生にあったかつての生活を再認識していきます。
震災からもうすぐ一年。5年後も10年後もこどもたちが健やかに育つことを願って。パパやママ、おじいちゃんやおばあちゃんもこどもたちのためにできることを見つけよう!笑顔で毎日を楽しむために、皆でつながり、一緒に考えていきましょう。この時代に親たちが何を考え行動しているのか発信する。
震災時における救援・復旧・復興の支援活動を一覧し補完検討できるアーカイブのインターネットサイトを制作、運営する。大小様々な活動を紹介し、紙媒体『震災リゲインプレス』も併用。復興に向かう地元住民や現地で支援を続ける支援者に直接、中間支援も行う。未来の為に記録を残し、備えを促したい。
これまで山口県で、映像制作と制作技術のシェアを行ってきました。3.11後、被災地から離れた場所での日常は、どのように変化したのか。東日本と西日本に生まれている情報の断絶、そこから生じる、被災地ではないとされる場所にすむ人々の震災への感覚を、映像で形にしたいと思っています。
みやぎ民話の会は35年にわたり県内の民話の語り手を訪ねてその語りを記録し会の刊行物として公表し、伝承の語りに触れる場としてのみやぎ民話の学校を開催してきた。今年の第7回は、東日本大震災で被災された語り手数名が歴史の提言者として体験を語り、その体験を共に分かち合う催しを企画している。
仙台市沿岸部の宮城野区南蒲生地区を中心に、復興まちづくりのサポートをしています。その活動の中で、震災前に撮影された写真に出会い、その写真と同じ場所を定点で記録していくことで、地域が復興していく様子を伝えたいと思います。
世界一熱い映画監督を目指す石巻出身のパッションと申します。石巻市民として自分には何ができるのか、そればかりをずっと考えていた所、わすれンに出会いました。幸い、自分には「映像」と「パッション」という切り口があるので、見る人が元気になれるような熱い映像を提供できればな、と思います。
高校生の震災映像ワークショップを高校生と目線が近い大学生という立場からお手伝いさせていただきたいと思っています。高校生たちが震災と向き合う際に生まれるであろう迷いなどを高校生に寄りそう形で支援していけたらと思っています。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いを生の声で記録し、様々な形でまちづくりに取り組む学生たちが、そうした被災地の復興へ現状をホンネで話し合うustream配信番組です。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
仙台、東京、海外の多様な学生が集まり、読者が震災の体験談をサイトに投稿できる参加型ウェブサイトを運営しています。今まで語る場を持たなかった人のために自らの思いを発信する機会づくり、東北の今を伝える記事やPodcastを通じて10年間の歩みと東北の魅力を再認識してもらう活動です。
飯舘村は緑豊かなまでいな村です。今も変わらない自然が恋しくて、7年の仮設住宅暮らしから村に戻ったのは高齢の方が約1割だけです。宮城県に一番近い国見仮設住宅から村に戻った方々の思いに寄り添い、いつか民話として語られる日を思いつつ、記録・発信していきたいと思っています。
仙台、東京、海外の多様な学生が集まり、読者が震災の体験談をサイトに投稿できる参加型ウェブサイトを運営しています。今まで語る場を持たなかった人のためが自らの思いを発信する機会づくり、東北の今を伝える記事やPodcastを通じて10年間の歩みと東北の魅力を再認識してもらう活動です。
仙台市の内陸部にあるごく一般的な住宅地。被害は目立たないながら、ここにも震災があって途方にくれる人たちが大勢います。そんな日本のどこにでも起こり得る住宅地の被災から復興までの道程を、住民の目線で記録していきたいと思います。
震災で失われた町並みや家、慣れ親しんだ場所…風景の変容とともに、場所の思い出も薄れていきます。ふとしたきっかけで思い出される家族のこと、街のこと、記憶のかけらを拾って、それぞれの物語を記録していきたいと思います。
仙台市若林区荒浜の住宅跡地を拠点に海辺の図書館という取り組みをしています。住むことのできなくなった地域のこれまでの暮らしや文化を音声やテキストで記録、写真と共に設置し、たくさんの方に荒浜の魅力を発信できればと考えています。未来を考えるためのアーカイブづくりを目指します。
水源や滝など水辺に祀られてきた「水神」「不動尊」などについて聞き取り調査をすることで、地域の人々と水の歴史や文化を記録しまとめる「水の神さま」プロジェクトを2008年から行ってきました。これから、東日本大震災による被害状況も追加調査し記録していきます。
I'm one of residence in Fukushima and I want to record all the action we are doing especiallythe present action in Fukushima.
東京で映画制作をしています。キャスティング、メイキングとして「マイバックページ」「CUT」「コドモのコドモ」など。拙作「革命前夜」「阪東太郎の悲しみ」が仙台で上映。地元住民の顔と、労働風景を正面から撮りたいと思います。
高校生の震災映像ワークショップを高校生と目線が近い大学生という立場からお手伝いさせていただきたいと思っています。高校生たちが震災と向き合う際に生まれるであろう迷いなどを高校生に寄りそう形で支援していけたらと思っています。
女川福幸丸は女川が大好きで女川のために何かしたいという気持ちだけで集まった若者達の団体です。団体名には「女川の福幸(復興)に向かって船出しよう」という意味がこめられています。昨年10月に開催した音楽イベント「我歴stock」を皮切りに、これからも女川のためにできることを模索します!
東日本大震災から早くも2年が経過し、多くの人の頭から震災に対する意識が薄れ始めてきている中で、もう一度震災について考えてもらう機会、きっかけが作れたらいいと思い参加しました。被災地外の人に現地に立ってもらい肌で感じてもらうツアーを計画しています。
1971年岩手県生まれ。大学卒業後、映像制作会社勤務を経て公益法人や放送局などで取材・映像制作に従事。スポーツや観光業を中心に被災地の取材を継続中。右投げ両打ち。チームプレイx。変化球プライド。
私の出身は愛知県ですが、偶然にも東日本大震災を経験しました。震災直後の被害はあったものの生活に支障の出るものではありませんでした。そのため、私自身も本当の被災状況はわかりません。そんな人たちに伝えるために、私がこれから直接見て、聞いたものを少しでも多くの人に伝えられたらと思います。
東日本大震災により甚大な被害を受けた中野小学校区の復興を考える地域団体であった、旧中野小学校区復興委員会のメンバーで構成している「なかの伝承の丘保存会」。その活動のひとつとして、震災と中野小学校区のことを残し、伝えるための映像記録制作を行います。ばらばらになった住民との橋渡しを行いつつ「ふるさと」を…
震災の前後で、多くのことが大きく変わると思います。それらを保存し、意味づけし、発信することが、今後大きな課題となるでしょう。今の人だけでなく、未来への子どもたちへメッセージとして何か残せればとの思いで活動してます。
3.11で起ったこと、出てきた意見、見たものや感じたものを、10代後半から20代前半の方向けにアーカイブしたweb制作を行います。また、それらの内容を、センターにおさめます。
東北の景色や食文化、手仕事を記録したいです。津波、地震のもたらしたもの、原発事故によってもたらされたものを地元の方がどううけとめるのか、うけとめているのかにも心を向けていきたいと思います。
福岡女学院大学人文学部林田ゼミ(表現演習)では、地域間の交流授業「ローカルの不思議」プロジェクトに参加しています。その一環として、福岡における支援活動を調べ、取り組まれている方々の状況や復興への思い、抱えている課題などをうかがい、映像にまとめる活動に取り組みました。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
東日本大震災。本震は6分以上続き、そこから30分の間に震度5以上の余震が8回記録された。その「揺れ」によって引き起こされた様々な個人体験について、対話を通じて言語化する番組「対話の時間-いまいまのいま」を放送します。
女川福幸丸は女川が大好きで女川のために何かしたいという気持ちだけで集まった若者達の団体です。団体名には「女川の福幸(復興)に向かって船出しよう」という意味がこめられています。昨年10月に開催した音楽イベント「我歴stock」を皮切りに、これからも女川のためにできることを模索します!
写真をとり感じた今、世の中に足りてないもの(それは形のないものかもしれない)を見つけてみたいです。今まで遊びでやっていたPhotoShopが役立てるか不安でもあり、楽しみです。
自閉症の青年の母親です。知的にも重度なので、3・11の時には困ることが色々ありました。あの頃、どうだったか?何があればよかったか?あまり発信していない母親達の言葉を集める事が出来ないか…と。今だから始めようと思いました。会って聞くことを大切に少しずつ動いていきます。
震災後、福祉施設の仕事が激減したため、被災地の福祉施設と連携し、障がいのある人のアートによる仕事づくり支援をしています。被災地の福祉施設の現状や表出されていないケアする人の声を記録し、映像を通して社会化し、そこに内包される知恵や学びを共有できるような記録活動を行いたいと思います。
描く事を通して、何をどう考えるかを考える、子どもたちとのワークショップを考える、絵とは何かを考える。しばしば描く事から離れて考える。身体を動かしてボランティアをしてみる。滞在してみる。作ってみる。
女川の皆さんと共に活動しています。災害は日々の暮らしの中にあった身近な存在や、自然との対話の大切さに気づかせてくれました。「表現と対話」の場づくりを住民と共に考え、体験しながら、住民自らの目で故郷を見直し、居場所をつくり、新しい日常を踏み出すためのお手伝いをしています。
「いまこそ、風化を目標にかかげるときだ。忘れることがよいことをもたらすのなら果敢にものごとを忘れよう」(『風化術』)東日本大震災の罹災をつたえる「語り部」を記録する。罹災とは、直接的な被害にかぎらず、二次被害もふくめる。記録のための記録ではなく、復興のための記録を完遂する。
こんにちは浅沼碧海です。僕は八丈島という小さな美しい島で生まれ育ちました。広い世界が見たくて、たくさんの事を知りたくて東京に出てきました。今この瞬間をこの目で見たくて宮城に来ました。自分の足で行動し見ることはメディアにはないものを感じれる。少しでもそれに近いものを届けたい。
以前、僕が新潟で震災復興の活動をしていたとき「子どもがいることで私は救われた。」という両親の話を聞きました。きっと今回の震災でも子どもは「希望」なのだと思います。被災地を中心に子どもたちの『今』を等身大で記録し、発信したいです。
女川の皆さんと共に活動しています。災害は日々の暮らしの中にあった身近な存在や、自然との対話の大切さに気づかせてくれました。「表現と対話」の場づくりを住民と共に考え、体験しながら、住民自らの目で故郷を見直し、居場所をつくり、新しい日常を踏み出すためのお手伝いをしています。
イェール大学で文化人類学とデータサイエンスの勉強をしており、個々人の複雑な人生を形に残すことを目標に、特に過去の記憶や語りをテーマに勉強しています。また、高校生の頃から写真や映像の活動も続けてきています。当センターではアーカイブの整理や記録の発信の活動に関わる予定です。
1993年福島県浪江町生まれ。2021年から震災当時子どもだった若者たちとオンライン上で自らの体験や思いを発信する。震災を特別な話にしない「ゆるくフラットに震災について語る会」を配信。被災程度や地域を問わず若者たちが震災について語り合う「みんなが主役のカフェトーク」実行委員。
震災後様々な映像を撮り続けていますが、映像は将来へ向けての保存・公開の意義や役割が大きいと思っています。その意味でわすれン!センターが長期的な活動を続けられること、自分もそれに何か役立つことをしたいと考えています。
相馬高校放送局は震災直後から作品を継続的に制作してきました。震災に対してその年ごとに抱いた思いを、大人の介入なしに作品にしています。震災時に福島県の高校生がどんな感情を抱いてたのかがよく伝わるという評価を多くの方にいただいています。作品をもとに震災についての対話の場を持ちたいと考えています。
映画の監督をしています濱口と言います。現在は沿岸部で津波被害に遭われた方に、津波についてカメラの前で語って頂いています。それぞれの方にとって、言い尽くせない体験だったのは間違いありません。ただ、この言葉をこの先の100年、残していかなくてはならないと今は強く感じています。
1981年、宮城県仙台市生まれ。DJやイベントオーガナイザー、音楽レーベルでの活動を経て、現在は被災地から音楽の力で復興に挑戦中。市民と音楽を交え対話する場として、せんだいメディアテークと共催で「くろい音楽室」という文化イベントも主宰。
仙台、東京、海外の多様な学生が集まり、読者が震災の体験談をサイトに投稿できる参加型ウェブサイトを運営しています。今まで語る場を持たなかった人のためが自らの思いを発信する機会づくり、東北の今を伝える記事やPodcastを通じて10年間の歩みと東北の魅力を再認識してもらう活動です。
大きな出来事があったその場所で、今話されていることばやそこにある景色を、伝わる形で残していきたいと同大学院の小森はるかと共に活動しています。また同時に、その場所にいない人に対しての発信もしていきます。私は主に文章、写真、絵を用いた記録、また伝わっていくものを作ることが出来たら、と思っています。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いを生の声で記録し、様々な形でまちづくり取り組む学生たちが、そうした被災地の復興の現状をホンネで話し合う番組を、各1つの地域を対象にしてUstreamで配信します。
大きな被災を経験した仙台市沿岸部に眼差しを向け、風土とともにある地域の姿を伝えていきたいと思います。住民の皆さんから語られる言葉をとおして「今」を見つめ、「これまで」と「これから」を考えていきたいと思っています。
在日留学生としては、震災後の在日外国人の暮らしに関心を持っています。在日外国人に関する記録をしたいし、外人の視点で日本国民の見えない所を見つけたいです。震災復興中の外人の生活から日本の本当の姿を掘り起こしたいです。
震災時における救援・復旧・復興の支援活動を一覧し補完検討できるアーカイブのインターネットサイトを制作、運営する。大小様々な活動を紹介し、紙媒体『震災リゲインプレス』も併用。復興に向かう地元住民や現地で支援を続ける支援者に直接、中間支援も行う。未来の為に記録を残し、備えを促したい。
NPO法人20世紀アーカイブ仙台の『仙臺しみんアーカイ部』のメンバーとして企画等に参加していきます。自分がすむまち『仙台市』の今のこれからを発信することに関わっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
北海道大学で社会学を学んでいる学生です。マイノリティと呼ばれる人々の生活の論理を聞き、残すことに関心があります。松本家計画では、福島県双葉群葛尾村に、学生時代から通う人々が、何を考えて、どのように生まれ育ちの場所ではない葛尾村に通うことを意味づけしているのかについて記録しています。
ダンスがきっかけで関わりを持つことになったダウン症の男性と、彼の母親へのインタビューを記録します。私とは異なる言葉を持っているその男性と、そんな彼を見守る母親の言葉に耳を傾けることから、これからの未来・希望について考えてみたいと思います。
東日本大震災から影響を受けた地域の風景や人びとの語りを、映像で記録していきます。いわゆる「記録」が陥りがちな硬直した視線から、(撮る側も観る側も)自由になるような映像、あるいは上映の機会をつくっていければと考えています。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
IMAYO!!は、太白区中央市民センターで活動している大学生企画団体です。震災後に企画したイベントを、映像として残して、次世代に繋げたいのでこのセンターを利用していきたいです。
東京に生まれ育ち、学生時代から全村避難の解除された福島県双葉郡葛尾村を訪れています。その中で村出身の方と知り合い、帰還困難区域の前に建つ、その方の生家を訪れるようになりました。一軒の家を通して見た震災や復興、その土地の歴史とこれからに関心を持っています。
水源や滝など水辺に祀られてきた「水神」「不動尊」などについて聞き取り調査をすることで、地域の人々と水の歴史や文化を記録しまとめる「水の神さま」プロジェクトを2008年から行ってきました。これから、東日本大震災による被害状況も追加調査し記録していきます。
仙台、東京、海外の多様な学生が集まり、読者が震災の体験談をサイトに投稿できる参加型ウェブサイトを運営しています。今まで語る場を持たなかった人のためが自らの思いを発信する機会づくり、東北の今を伝える記事やPodcastを通じて10年間の歩みと東北の魅力を再認識してもらう活動です。
「公助」からも「共助」からも取り残され、「社会的に孤立した」状態で震災を迎えた人たちを記録します。東北地方を襲った今回の大震災を、首都圏に生きる「私たちの」問題として考え直すきっかけをつくりたいです。
高校生の震災映像ワークショップを高校生と目線が近い大学生という立場からお手伝いさせていただきたいと思っています。高校生たちが震災と向き合う際に生まれるであろう迷いなどを高校生に寄りそう形で支援していけたらと思っています。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いをなもの声で記録し、様々な形でまちづくりに取り組む学生たちがそうした被災地の復興の現状をホンネで話し合う番組を、各回1つの地域を対象にしてUstreamで配信します。
女川の皆さんと共に活動しています。災害は日々の暮らしの中にあった身近な存在や、自然との対話の大切さに気づかせてくれました。「表現と対話」の場づくりを住民と共に考え、体験しながら、住民自らの目で故郷を見直し、居場所をつくり、新しい日常を踏み出すためのお手伝いをしています。
I want show and document the life of my co filipin's about the last Earthquake and Tsunami vtctins.Yoroshiku onegaishimasu!!
がんばろう気仙沼は、気仙沼出身者。気仙沼在中者、気仙沼へボランティアに来た方で構成されています。市民向けに罹災証明の震災写真のサポートで始めました。8月15日現在で約4500枚あります。海外メディア、台湾、スイス、フランス、ドイツや各団体とコラボして説明会などのイベントに提供します。
「東北の造形作家を支援する会」(SOAT ソアト)は東北の芸術の創作および発表活動を支援し、地域社会の芸術文化の向上に寄与することを目的に2010年に設立されたNPO法人です。現在は被災地の作家や学校関係者への画材支援や、こどものためのワークショップなどアートの面から復興支援をしています。
3.11の後、様々な物をみてきました。建物や土地の被害はもちろん、人々の心にも多くの被害が降りそそぎました。私たちはこれを忘れてはいけません。後世にも語り継ぐべく、私はこの思いを伝えやすい写真や映像に込めたいと思います。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いを生の声で記録し、様々な形でまちづくりに取り組む学生たちが、そうした被災地の復興の現状をホンネで話し合う番組を、各回1つの地域を対象にしてUstreamで配信します。
宮城県石巻出身。東日本大震災当時は石巻市門脇小学校6年生。現在は、石巻を中心にアウトロー語り部として活動中。その他に、オンライン配信「ゆるくフラットに震災について語る会」やオンラインイベント「みんなが主役のカフェトーク~今さら!?今だから!!震災トーク~」の運営をしている。
東京で映画製作をしています。今回、友人と一緒に、復興に向かう宮城をドキュメンタリー映画として記録に残したいと思っています。100年先も残せるようなものにしたいと思っています。ぜひ宮城の皆さんと一緒に作り上げたいです。
震災後、何度か福島・宮城・岩手へ訪れ、そこに暮らす人達と話し、少しずつ映像を撮ってきました。いくつかの場所でのある日のある人。報道や情報からはこぼれ落ちてしまう人々の姿や佇まいを見つめ記録したいです。
3月11日以降私達を取り巻くメディアのあり方が大きく様相を変えました。膨大な情報の中で何を選ぶのかが重要になりますが、その情報というのも人がつくるものです。それを記録するのも人が行うことです。何を記録しどのように、どんなかたちで残していくのか。記録する方法を考えていきます。
参加した人が周りに伝えたくなるような、震災について考えるきっかけになるようなツアーを企画しています。少しでも多くの人に、震災について考え、伝えて欲しいと考えます。そのために私自身も、日々考え、学んで行きたいです。
東京プライドはセクシャル・マイノリティへの差別、偏見をなくし、正しい知識と理解を広め、セクシャル・マイノリティが生きやすい社会の実現を目指すことを目的とする非営利団体です。東北と東京をつなぐ事業を企画しています。
仙台定禅寺通でビッグイシューを販売する鈴木太氏と仙台市在住の門脇篤氏がお送りするネット中継「定禅寺ジャーナル ウェブ版」にあなたも参加できます!毎回テーマを設定しつつも脱線しまくりの105分。もちろんUSTREAMでもご鑑賞いただけます。レッツ・ディベート!
震災を通じて、「あたりまえに過ごす」ことって何だろう?と考えるようになりました。生活をする姿、暮らしを続けていく姿。何も飾らず、脚色せず、できるかぎり実直に見続けていきたいです。
東日本大震災により被災された方々から、発災直後からどのような体験をし、行動をとったか、そしてどのような想いを抱えたかを聞き取り、文章として残す事業に取り組んでいます。そのことで震災を風化させることなく後世へと語り継ぐことができればと考えています。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
1998年の山元町総合計画には「201X年の山元町」と題し、理想とする山元町の姿を活き活きと記したテキストが収録されている。ここに託され受け継がれてきた町への思いが震災の痛みの中で消えてしまわぬよう、災害FM「りんごラジオ」による朗読とともに2013年2月現在の山元町を住民の手で記録する。
女川福幸丸は女川が大好きで女川のために何かしたいという気持ちだけで集まった若者達の団体です。団体名には「女川の福幸(復興)に向かって船出しよう」という意味がこめられています。昨年10月に開催した音楽イベント「我歴stock」を皮切りに、これからも女川のためにできることを模索します!
仙台市若林区荒浜にて、荒浜小学校、七郷中学校の卒業生が中心となって「HOPE FOR PROJECT」という活動を行っています。繋がりが失われた町に、もう一度笑顔や思いを共有出来る時間を作れればと3月11日を中心に活動しています。
高校生の震災映像ワークショップを高校生と目線が近い大学生という立場からお手伝いさせていただきたいと思っています。高校生たちが震災と向き合う際に生まれるであろう迷いなどを高校生に寄りそう形で支援していけたらと思っています。
水、空気、大地私たちの周囲の世界が311で全部壊れた?その大切な存在に改めて気づいても、もう遅過ぎた?いいえ、“汚れちまった悲しみ”を嘆く前に今何をしたらいいのか一緒に考えて、求めて私たちと歩いて行きませんか?
表現活動はこどもだけでなく、大人にも大切な感性刺激だと思います。ソアトでは観るだけでなく、誰でも気軽に参加できる身近な創作機会の提供を目的にワークショップやイベント等、様々な活動をしています。表現するチカラが持つ元気や勇気、日々のちいさな感動をぜひ見つけてほしいと思います。
楽器支援をする活動を仙台市内の有志で行っているグループです。これまでに気仙沼、石巻、陸前高田にて高校生やアマチュアミュージシャンへ支援活動を行っています。楽器支援の報告を通して音楽家の今とこれからを記録し申請の過程を県内の音楽家と共に考えていきたいと思います。
仙台市沿岸津波被災エリアに居住されていた方々の生活再生を支援しています「仙台平野再生支援ボード」などで、被災者の生活や生業再生を支援しています。地元のコミュニティFM局とも連携しながら、地元の今を発信しています。
東日本大震災の被害にあわれた住民の方々の復興まちづくりに対する思いを生の声で記録し、様々な形でまちづくりに取り組む学生たちが、そうした被災地の復興の現状をホンネで話し合う番組を、各回1つの地域を対象にしてUstreamで配信します。
私は無線・電波に関心を持つ社会人学生等が集まったサークルの代表を務めています。非常時に有効な通信手段とされるアマチュア無線と防災活動の連動についても研究しています。3.11から10年以上経過していることも踏まえ、非常時の情報通信(アマチュア無線やラジオ局等)に実際に関わった人たちへのインタビューを通…
仮設住宅という制限ある日常生活へのマンネリ化や居住環境のストレスを緩和するため、そして住民同士の関係性や交流の場としてアートワークショップや芸術鑑賞、音楽にてコミュニティー支援を行う。日々変化し続ける仮設住宅と支援する人々の声を記録し発信する。
震災直後~数週間、私が住んでいる仙台都市部ではライフライン・燃料・食料等が無くなり、かつてない混乱に陥った。記憶が曖昧になる前に、混乱を再び起こさないために、震災直後~数週間の詳細について+これからについてインタビューを行い、何が必要かを見つけたい。お話し頂ける方募集しています。
震災前、昭和59(1984)年から、仙台市内や宮城県内の沿岸部を巡っては、風景や建物の写真を撮ったり調査を行ったりしてきました。それは震災を経た現在でも続けており、記録した写真や資料は膨大な量になりました。これらを整理し、ウェブサイトや展示などで公開していきます。
被災地でのボランティア状況や観光情報を直接現地を訪問して収集しています。その被災地情報をボランティアツアーや学習プログラムを企画する資料として、旅行会社や学校へ発信してます。私たちは被災地から「来てほしい」と「行きたい」の声をつなぐ橋渡し存在になりたいと考えています。
東日本大震災を経験し、自分にも何かやれることはないのかと思い、参加させていただきました。震災の爪痕が残っているということ、それが時間とともに風化し、忘れさられることを防ぎ、伝えていきたいです。主に定点観測をベースとした被災地ツアーを企画していきます。
- 2026年2月12日展示のご案内【石川、長崎】
- 2026年1月28日星空と路—3がつ11にちをわすれないために—(202…
- 2025年7月24日〈終了〉【展示協力】9月6日ブラックアウトのなかで …
- 2025年3月09日〈終了〉星空と路—3がつ11にちをわすれないために—…
3がつ11にちをわすれないためにセンター
(せんだいメディアテーク 企画・活動支援室内)
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町2-1
TEL 022-713-4483